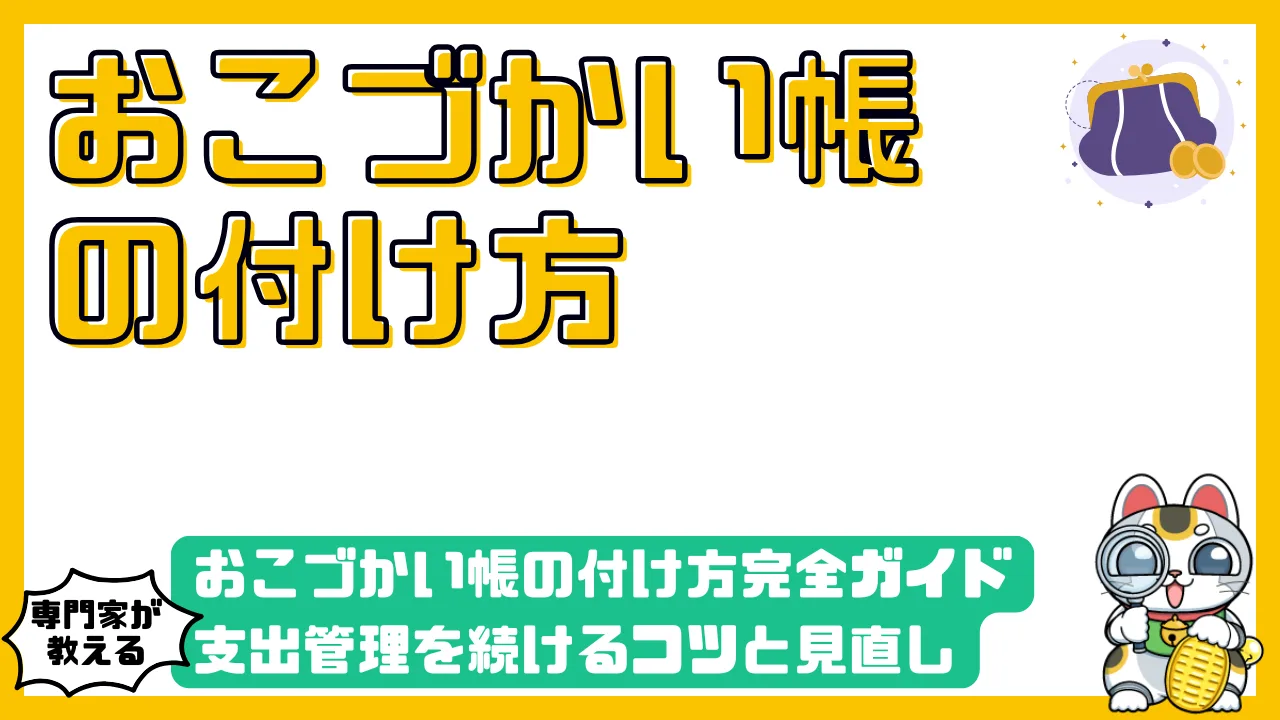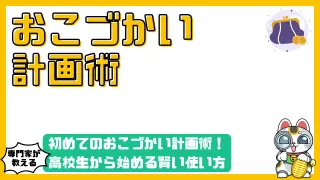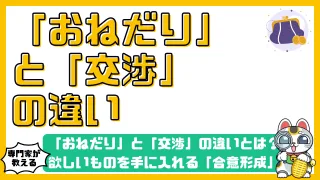本ページはプロモーションが含まれています。
このページの内容の理解度をクイズでチェック!
目次
はじめに
「今月も、なぜかお金がない…」「何に使ったか覚えていないお金が多い」。
高校生や社会人になったばかりの頃、そんな経験はありませんか?
お金の管理は、大人になってから突然できるようになる魔法ではありません。日々の小さな習慣から身につける「技術」です。その最も基本的で強力な第一歩が、「おこづかい帳(家計簿)」をつけることです。
「おこづかい帳なんて、面倒くさい」「節約のためでしょう?」と思うかもしれません。しかし、その本当の目的は、単なる節約ではなく、「自分のお金の使い方を知り、将来のために計画的に使う力を養う」ことにあります。
この記事では、おこづかい帳を「なぜつけるのか?」という基本的な目的から、多くの人が挫折してしまう理由、そして「どうすれば続けられるのか?」という具体的なコツまで、網羅的に解説します。この記事を読めば、支出を記録する習慣がいかに重要か、そしてそれがあなたの未来にどう役立つかが理解できるはずです。

金利が低いからこそ、手数料というコストをいかに削減するかが重要です。優遇条件を理解し、最もお得に使える方法を見つけることが、賢い金融生活の第一歩となります。
おこづかい帳とは? お金の流れを把握する「見える化」の第一歩
まず、おこづかい帳の最も基本的な目的を確認しましょう。
それは、「自分のお金の流れを『見える化』する」ことです。
おこづかい帳は、いつ、何に、いくらお金を使ったか(支出)、そして、いつ、いくらお金が入ったか(収入)を記録するためのノートやツールのことです。
多くの場合、私たちは「なんとなく」お金を使っています。コンビニで買ったジュース、友達とのカフェ代、ふと目に入った雑貨。一つひとつは少額でも、積み重なれば大きな金額になります。しかし、その「なんとなく」使ったお金は、記憶からすぐに消えてしまいます。
おこづかい帳をつけることで、この「なんとなく」使っていたお金が具体的な「数字」と「項目」として目に見えるようになります。これが「見える化」です。
自分が1ヶ月に「何に」「いくら」使っているのか。
これを正確に把握(はあく)することが、上手なお金の使い方を学ぶための、全ての始まりとなります。
まずは「支出」の記録から始めよう
収入(アルバイト代やおこづかい)が毎月ほぼ決まっている高校生や新社会人の場合、最初は「支出」だけを記録することから始めるのが簡単でおすすめです。
入ってくるお金より、出ていくお金を管理する方が、お金の使い方を改善する上では即効性があります。
形式は自由! 自分に合った方法を見つける
「おこづかい帳」と聞くと、専用のノートを思い浮かべるかもしれませんが、形式は問いません。
- ノート: 100円ショップでも売っている専用ノートや、普通の方眼ノートでも構いません。手書きで記録することで記憶に残りやすいメリットがあります。
- スマホアプリ: 無料で高機能な家計簿アプリがたくさんあります。レシートを撮影するだけで自動入力されたり、銀行口座やクレジットカードと連携して自動で記録されたりするものが人気です。
- Excel(スプレッドシート): パソコン操作が得意な人や、自分で細かくカスタマイズしたい人に向いています。
大切なのは、どのツールを使うかではなく、「自分にとって最も続けやすい方法を選ぶ」ことです。

金利が低いからこそ、手数料というコストをいかに削減するかが重要です。優遇条件を理解し、最もお得に使える方法を見つけることが、賢い金融生活の第一歩となります。
なぜ記録が続かない? 挫折の9割「完璧主義の罠」の正体
「よし、今日からおこづかい帳をつけるぞ!」と意気込んで始めたものの、3日も経たずに挫折してしまった…そんな経験はありませんか?
多くの人がおこづかい帳を続けられない最大の理由は、「面倒くさい」「レシートを溜めてしまう」ことですが、その根底には「完璧主義の罠(わな)」が潜んでいます。
「完璧主義の罠」とは、
「毎日、1円単位で完璧に記録しなければならない」
と思い込み、それがプレッシャーになってしまうことです。
そして、一度でも記録を忘れたり、計算が1円でも合わなかったりすると、「ああ、もうダメだ」「自分には向いていない」とすべてが嫌になり、記録自体をやめてしまう。これが、最もありがちな挫折パターンです。
1円のズレは気にしない。「使途不明金」を恐れない
おこづかい帳の目的は、会計士のように正確な帳簿を作ることではありません。自分のお金の「傾向」を把握することです。
レシートをもらい忘れたり、いくら使ったか思い出せなかったりすることもあるでしょう。そんな時は、無理に思い出そうとせず、「使途不明金」としてザックリ記録してしまって構いません。
1円や100円のズレを気にして記録が止まってしまうことこそが、最大の間違いです。大切なのは、完璧に記録することではなく、途中でやめずに「続ける」ことです。記録自体が目的になってはいけません。

金利が低いからこそ、手数料というコストをいかに削減するかが重要です。優遇条件を理解し、最もお得に使える方法を見つけることが、賢い金融生活の第一歩となります。
挫折しない! 支出管理を「続ける」ための3つの簡単テクニック
では、どうすれば「完璧主義の罠」に陥らずに、おこづかい帳を続けることができるのでしょうか。
継続のコツは、ただ一つ。「徹底的にハードルを下げる」ことです。
ここでは、誰でも簡単に実践できる3つのテクニックを紹介します。
テクニック1:記録のハードルを極限まで下げる
「毎日寝る前に記録する」と決めても、疲れて寝てしまう日もあります。自分の生活リズムに合わせ、無理のないルールを作りましょう。
- 毎日ではなく「週末にまとめて」記録する
- 「レシートが5枚溜まったら」記録する
- 「お金を使ったその日」に記録する(寝る前など)
また、最近のスマホアプリは非常に優秀です。
レシートを撮影するだけで品目や金額を読み取ってくれる機能や、電子マネーやクレジットカードと連携して、支払った瞬間に自動で記録してくれる機能もあります。
面倒な「入力作業」を技術の力でカバーすることで、記録の負担を大幅に減らすことができます。
テクニック2:費目をシンプルにする(固定費と変動費)
挫折するもう一つの大きな原因が、「費目(ひもく)」の分けすぎです。
費目とは、「食費」「交際費」「交通費」「趣味」といった支出の分類のこと。
これを最初から細かく「食費→(朝ごはん・昼ごはん・お菓子・飲み物)」のように分けすぎると、記録のたびに「これはどの項目だ?」と悩むことになり、それ自体が大きなストレスになります。
そこでおすすめなのが、最初は「固定費」と「変動費」の2つだけに分ける方法です。
- 固定費: 毎月(あるいは毎年)必ず、ほぼ決まった金額が出ていくお金。
- (例:家賃、スマホ代、奨学金の返済、サブスク代、保険料など)
- 変動費: 月によって金額が変わる、日々の生活で使うお金。
- (例:食費、交際費、交通費、趣味代、日用品費など)
まずはこの2つに分けるだけでも、「自分が自由に使えるお金(変動費)は毎月いくらか」が明確になり、お金の流れは十分に把握できます。慣れてきたら、変動費の中身を「食費」「交際費」「その他」の3つに分ける、というように少しずつ増やしていけばOKです。
テクニック3:習慣化の仕組みを作る
記録することは「作業」であり、面倒なものです。これを続けるには、「できた!」という小さな達成感を積み重ねることが重要です。
- 記録できたら自分を褒める
- カレンダーにシールを貼る
- アプリの記録グラフが埋まっていくのを見て楽しむ
どんな些細なことでも構いません。記録を「面倒な作業」から「楽しいゲーム」に変える工夫(習慣化のご褒美)を見つけましょう。

金利が低いからこそ、手数料というコストをいかに削減するかが重要です。優遇条件を理解し、最もお得に使える方法を見つけることが、賢い金融生活の第一歩となります。
記録だけで満足はNG!「見直し(振り返り)」こそが最も重要
おこづかい帳を続けることに成功したら、次のステップに進みましょう。
実は、おこづかい帳は「記録して終わり」ではありません。むしろ、記録したデータを見直すこと(振り返り)こそが、最も重要です。
記録はあくまで「過去のデータ」です。そのデータを見て、反省し、次の行動につなげなければ、おこづかい帳をつけている意味が半減してしまいます。
この「見直し」こそが、あなた自身の「お金の管理能力」を育てる核心部分です。
具体的な「見直し」の方法とは?
見直しは、月末や週末など、月に一度「見直しタイム」を設けて行うのが効果的です。
例えば、記録を見返して「今月は食費が(予算より)5千円も多い」という事実に気づいたとします。
この時、やってはいけないのが、「来月は食費を一方的に5千円減らそう」と結果だけを見て焦ることです。
重要なのは、「なぜそうなったのか?」という原因を分析することです。
- 「飲み会や外食が多かったからかな?」
- 「ストレスでコンビニスイーツを買いすぎたかも」
- 「自炊をサボった日が多かった」
このように原因を分析することで、初めて具体的な対策が見えてきます。
原因が「飲み会が多かった」なら、「来月は飲み会の回数を1回減らそう」あるいは「1回の予算を決めよう」といった、現実的な次の行動(対策)を立てることができます。
ただ記録した数字(結果)を見て落ち込むのではなく、なぜそうなったか(原因)を冷静に分析すること。これが「見直し」の核心です。
見直しから「次の目標」へつなげる
見直しをしたら、必ず次の月の「使い方の目標」を立てましょう。
- 「何となく使ったお金(使途不明金やコンビニ代)を〇%減らす」
- 「今月は〇〇(趣味)を我慢できたから、来月も続けよう」
- 「自炊を週に2回増やす」
「記録(過去)→ 見直し・分析(現在)→ 行動目標(未来)」というサイクルを回すこと。
これこそが、おこづかい帳をつける真の目的なのです。

金利が低いからこそ、手数料というコストをいかに削減するかが重要です。優遇条件を理解し、最もお得に使える方法を見つけることが、賢い金融生活の第一歩となります。
記録習慣が未来を変える? おこづかい帳が育む「自己管理能力」
おこづかい帳を続けることは、単なる節約術を学ぶことではありません。
支出の記録を「自己分析」の一環として捉えてみましょう。
「自分は食費には無頓着だけど、本や学びにはお金を使いたいんだな」
「友達と過ごす時間(交際費)を一番大切にしているんだな」
このように、支出の記録は、自分が何にお金を使いたいのか、何を大切にしているのか(価値観)を知るための強力なツールとなります。
お金を計画的に使う練習は、そのまま「自己管理能力」を養う訓練(くんれん)になります。
「今月は、あの服を買うために、飲み会を1回我慢しよう」
「来月の旅行のために、今週はコンビニ通いをやめよう」
目先の欲求をコントロールし、将来のより大きな目標のためにお金を計画的に使う。この練習で得られる「小さな成功体験」の積み重ねが、お金に対する自信と、将来の大きな目標を達成するための「自己管理能力」を育ててくれるのです。
おこづかい帳を続ける上で最も大切にすべき心構えは、記録したデータを見直し、分析し、次の行動目標を立てるというサイクルを回し続けることです。
毎日記録することや、完璧に記録することは「手段」にすぎません。本来の目的である「お金の管理能力を養う」ことを見失わないようにしましょう。

金利が低いからこそ、手数料というコストをいかに削減するかが重要です。優遇条件を理解し、最もお得に使える方法を見つけることが、賢い金融生活の第一歩となります。
まとめとやるべきアクション
今回は、おこづかい帳の基本的な目的から、挫折しないための具体的なコツ、そして最も重要な「見直し」の方法までを解説しました。
おこづかい帳のポイント
- 目的は「見える化」: 自分が何にお金を使っているか、お金の流れを把握することが第一歩。
- 挫折の原因は「完璧主義」: 1円のズレや数日の記録漏れは気にせず、「続ける」ことを最優先する。
- 継続のコツは「ハードルを下げる」: アプリを活用し、費目は「固定費」「変動費」などシンプルに。
- 「見直し」こそが核心: 記録して満足せず、月末などに「なぜ使ったか」を分析し、次の行動目標を立てる。
- 育つのは「自己管理能力」: お金の管理は、自分の価値観を知り、将来の目標を達成するための訓練になる。
おこづかい帳は、あなたのお金の使い方を映し出す「鏡」です。
まずは難しく考えず、今日から1週間だけ、使ったお金(レシートや電子マネーの履歴)を、ノートやスマホアプリに記録してみませんか?
その小さな一歩が、あなたのお金との付き合い方を大きく変えるきっかけになるはずです。

金利が低いからこそ、手数料というコストをいかに削減するかが重要です。優遇条件を理解し、最もお得に使える方法を見つけることが、賢い金融生活の第一歩となります。
このページの内容の理解度をクイズでチェック!
免責事項
本記事は、一般的な企業・業界情報および公開資料等に基づく執筆者個人の見解をまとめたものであり、特定の銘柄や金融商品への投資を推奨・勧誘するものではありません。また、記事内で取り上げた見解・数値・将来予測は、執筆時点の情報に基づくものであり、その正確性・完全性を保証するものではありません。今後の市場環境や企業動向の変化により、内容が変更される可能性があります。
本記事に基づく投資判断は、読者ご自身の責任と判断において行ってください。 本記事の内容に起因して生じたいかなる損失・損害についても、当サイトおよび執筆者は一切の責任を負いません。本記事は金融商品取引法第37条に定める「投資助言」等には該当せず、登録金融商品取引業者による助言サービスではありません。