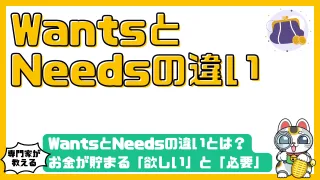本ページはプロモーションが含まれています。
このページの内容の理解度をクイズでチェック!
目次
はじめに
高校生や社会人になったばかりの頃、友人関係はとても大切なものです。しかし、その大切な関係に「お金」が絡むと、事態は一変することがあります。
「悪いけど、今月ピンチで。少し貸してくれない?」
「ごめん、財布忘れた!今日のランチ代だけ立て替えておいて」
こんな風に頼まれたら、あなたはどうしますか?
「親しい友達だから助けたい」「断ったら冷たいと思われるかも」と悩むのは当然です。しかし、軽い気持ちで行ったお金の貸し借りが、修復不可能なほどの「金銭トラブル」に発展し、かけがえのない友情を失うケースは、残念ながら非常に多く存在します。
この記事では、なぜ友達とのお金の貸し借りを避けるべきなのか、その具体的なリスクと、万が一の際の対処法、そして何より大切な「友情の守り方」について、詳しく解説していきます。
金融リテラシーとは、単にお金を増やす知識だけではありません。お金によって人間関係を壊さないための「守りの知識」も同じくらい重要なのです。

お金の問題は、友情という目に見えない価値を簡単に壊してしまう力を持っています。この記事で学ぶのは、お金の計算ではなく、「信頼関係」を守るためのルールです。
なぜダメ?友達間の貸し借りが友情を壊す根本理由
まず大原則として、「親しい仲でも、友達同士のお金の貸し借りは避けるべき」です。
多くの人が「お金が返ってこないかもしれないから(経済的リスク)」を一番の理由に挙げますが、実はそれ以上に深刻な問題があります。
それは、「信頼関係が悪化し、友情が壊れるリスク」です。
お金を貸すと、貸した側と借りた側の間に「債権者(さいけんしゃ:お金を返してもらう権利がある人)」と「債務者(さいむしゃ:お金を返す義務がある人)」という、それまでの対等な友人関係とは異なる「上下関係」が生まれてしまいます。
- 貸した側は「いつ返してくれるんだろう」と気になり始めます。
- 借りた側は「返さないと」というプレッシャーを感じ、どこか引け目を感じるようになります。
このアンバランスな関係が、お互いの心に小さなトゲを生みます。
金額の大小は関係ありません。「100円だから大丈夫」「ジュース1本だから」という少額の貸し借りこそが危険です。少額だからこそ「まあ、いいか」と曖昧になりやすく、それが積み重なって常態化し、金銭感覚のズレや不信感につながるのです。(「少額なら問題ない」というのは大きな誤解です)
「友達だからこそ、お金のことはきっちりしたい」ではなく、「友達だからこそ、お金の関係を持ち込まない」という意識が重要です。時には、大切な友情を守るために「ごめん、貸せない」と断る勇気を持つことも必要になります。

貸し借りの最大のリスクは、お金を失うこと(貸し倒れ)ではありません。お金はまた稼げますが、一度失った信頼や友情を取り戻すのは極めて困難です。
貸す側・借りる側 双方が負う「見えないリスク」
お金の貸し借りは、貸した側にも借りた側にも、目に見えにくい大きなリスクをもたらします。具体的にどのようなリスクがあるのか、双方の立場で見ていきましょう。
貸した側が負うリスク
- 貸し倒れ(返済されない)リスク
文字通り、貸したお金が返ってこない可能性です。「すぐ返す」という言葉を信じても、相手の事情が変わったり、連絡が取れなくなったりすることはあり得ます。 - 催促(さいそく)のストレス
これが人間関係において最大のリスクです。約束の日を過ぎても返済がない場合、貸した側から「あのお金、どうなってる?」と切り出さなければなりません。- 「お金にがめついと思われたくない」
- 「友達関係を壊したくない」
- 「相手も大変なのかもしれない」
こんな思いから、親しい仲だからこそ「返して」と言い出しにくいものです。この「言いたいけど言えない」状態が、非常に大きな精神的ストレス(気まずさ)となります。
相手がSNSで楽しそうに遊んでいる投稿を見れば、「遊ぶお金はあるのに、なぜ返してくれないんだ」と不信感が募り、友情は急速に冷え込んでいきます。
借りた側が負うリスク
- 信用失墜(しんようしっつい)のリスク
借りた側も、期限までに返せなければ「約束を守れない人」「お金にだらしない人」というレッテルを貼られてしまいます。
一度失った信用を取り戻すのは大変です。「あの人はお金を借りても返さない」という評判は、その友人関係だけでなく、共通の知人やコミュニティ全体に広がる可能性もあります。 - 精神的なプレッシャー
「返さなければならない」という義務感は、常に心の重荷となります。貸してくれた友人と顔を合わせるのが気まずくなり、無意識のうちに避けるようになってしまうことも。結果として、自ら友人関係を遠ざけてしまうことになります。
このように、貸し借りは双方にとって精神的な負担が大きく、関係を悪化させる火種にしかならないのです。

「貸して」と言われた瞬間、貸す側は「返ってこないかも」「催促しにくい」というストレスを、借りる側は「返せないかも」「信用を失うかも」というリスクを同時に背負うことになります。
やむを得ず貸す場合の「最低限の約束事」
原則は「貸さない」ことですが、冠婚葬祭や緊急の医療費など、どうしても断りきれない事情があるかもしれません。
もし、やむを得ず貸すという判断をした場合は、後々のトラブルを防ぐために、必ず「ルール」を決めて「記録」に残しましょう。これは相手を信用していないからではなく、お互いの「誤解」を防ぎ、友情を守るためです。
1. 「借用書」または「記録」の作成
「友達なのに借用書(しゃくようしょ)なんて水臭い」と思うかもしれません。しかし、借用書や記録を作成する最大の目的は、「約束した内容を明確にし、お互いの『言った・言わない』を防ぐこと」です。
裁判沙汰にするための証拠(もちろん最終的には証拠になり得ますが)としてではなく、あくまで「約束を忘れないためのメモ」として機能させることが重要です。
大げさな書式でなくても構いません。以下の内容が明確になっていれば、チャットアプリ(LINEなど)やメールの履歴でも十分な記録となります。
- 誰が誰に(貸主と借主の名前)
- いくらを(正確な金額)
- いつ(貸した日付)
- いつまでに(返済期限)
- どのように返すか(一括か分割か、手渡しか振込か)
2. ルールの明確化
記録に残す際、特に以下の2点は曖昧にしてはいけません。
- 返済期限の明確化:「お金ができたら」「余裕ができたら」はNGです。「○月○日までに」と具体的な日付を決めます。
- 返済方法の確認:振込なのか、次に会った時に手渡しなのかを決めます。分割にする場合は、毎月いくらずつ、いつ払うのかまで決めましょう。
これらを決めて記録に残すことで、借りた側にも「返さなければ」という適度な緊張感が生まれます(これは副次的な効果です)。何より、貸した側が「いつ返ってくるんだろう」とモヤモヤするストレスを軽減できます。

「言った・言わない」は、信頼関係を破壊する最悪のトラブルです。借用書やチャット履歴は、裁判のためではなく、お互いの記憶違いによる誤解を防ぐための「友情の保険」だと考えましょう。
「すぐ返すから」が危険信号!よくあるトラブル事例集
「友達だから」「少額だから」という油断が、深刻なトラブルにつながります。ここでは、実際によくある失敗例を見ていきましょう。
ケース1:口約束による返済の遅延
- 状況:「ごめん、千円だけ貸して!すぐ返すから」と言われ、口約束で貸した。
- トラブル:「すぐ」がいつなのか分からず、1ヶ月経っても返済がない。催促するのも気まずくて言い出せない。相手は借りたこと自体を忘れているかもしれない。
- 解説:「すぐ」「近いうちに」といった曖昧な約束は、トラブルの元凶です。(「友達なら口約束で十分だ」という考えは危険です)
ケース2:少額の貸し借りの常態化
- 状況:「ランチ代が足りない」「ジュース奢って。次返すから」といった数百円単位の貸し借りが続いている。
- トラブル:貸した側は「またか…」と不満が溜まる。借りた側は少額のため罪悪感が薄れ、「まあいいか」と借りることがクセ(常態化)になる。
- 解説:少額であっても、お金は「貸し借り」です。積み重なれば高額になり、ある日突然、貸していた側が「今までの合計、○千円になってるんだけど」と切り出し、関係が破綻するケースです。
ケース3:利息の要求による関係悪化
- 状況:貸したお金がなかなか返ってこないので、イライラして「遅れたんだから、利息(りそく:借りたお金に追加して支払うお金)くらいつけてよ」と要求してしまった。
- トラブル:相手は「友達なのに利息取るのか!」と逆ギレ。友情は完全に崩壊。
- 解説:友達同士の貸し借りで利息を要求するのは、関係を終わらせる行為に等しいです。(「利息を取るのが当然だ」という考えは、友情関係には持ち込むべきではありません)そもそも個人間でお金(特に利息)のやり取りをすることは、たとえ少額でも法律(出資法など)に抵触するリスクを伴うため、絶対に避けるべきです。

「ちょっとだけ」「すぐ返す」という言葉は、金銭感覚がルーズになっているサインかもしれません。少額のゆるい貸し借りが、お互いの金銭感覚を麻痺させ、大きなトラブルの入り口となります。
友情もお金も守る!トラブルを未然に防ぐ最終結論
では、友人関係を大切にしながら、お金のトラブルを避けるには、最終的にどうすればよいのでしょうか。
1. 原則:「貸さない・借りない」を徹底する
これが最もシンプルかつ最強のトラブル回避策です。あなた自身が「友達からは絶対に借りない」と決め、同時に「友達にも絶対に貸さない」というルールを自分の中で確立することが重要です。
2. 「貸して」と言われた時の賢い対処法
もし友人に「お金を貸してほしい」と頼まれたら、どう対応するのがベストでしょうか。
- NGな対応
- 「冷たいと思われる」(ありがちな誤解)という理由で、仕方なく貸す。
- 「少額ならいいか」と、その場しのぎで貸してしまう。
- 気まずくて無視したり、聞こえないふりをしたりする。
- ベストな対応
「原則は断る。しかし、相手の事情を親身に聞いて、お金以外の方法で助けを提案する」ことです。 ステップ1:まずは「貸せない」意思を伝える
「ごめん、うちは親から『友達とは絶対にお金の貸し借りはしない』って厳しく言われてて…」
「お金のことはトラブルになるから、友達とはやらないって決めてるんだ。ごめんね」
(相手のせいではなく)自分のルールや家庭の方針として伝えると、角が立ちにくくなります。 ステップ2:理由を聞き、代替案を一緒に考える
ただ断って終わり(=冷たくする)のではなく、「でも、どうしたの?何か困ってることある?」と、相手を心配している姿勢を見せることが大切です。- 本当に困っている場合:
「それなら、親御さんに相談してみたら?」「学生なら学校の奨学金制度とか、公的な相談窓口(社会福祉協議会など)もあるみたいだよ」と、お金以外の「情報」や「知恵」でサポートします。 - 単なる浪費や遊びの場合:
「それなら今度、お金のかからない遊びをしようよ」と、別の提案をします。
- 本当に困っている場合:
3. 最後の心構え:貸すなら「あげる」覚悟で
それでもなお、あなたが「この友人を助けたい」と強く思い、貸すことを選ぶのであれば、それは「貸す」のではなく、「あげる(贈与する)」覚悟で渡してください。
- 返ってこなくても絶対に文句を言わない。
- 催促もしない。
- 自分の生活に一切支障が出ない、完全になくなっても構わない金額(お小遣いの範囲内)にする。
「貸した」と思うから「返してほしい」というストレスが生まれます。「あげた」と思えば、もし返ってきたらラッキー、くらいの気持ちでいられます。
もちろん、これは最終手段であり、推奨される方法ではありません。

「冷たい人」と思われることを恐れて貸すのは、本当の優しさではありません。お金で解決せず、親身になって相談に乗り、別の解決策を一緒に考えることこそが、本当の友情です。
まとめとやるべきアクション
友達とのお金の貸し借りは、金額の大小に関わらず、大切な「信頼関係」を壊す最大のリスクとなります。
- 基本原則:友達とは「貸さない・借りない」を徹底する。
- リスク:貸す側は「催促のストレス」、借りる側は「信用の失墜」という大きな精神的負担を負う。
- もしもの時:やむを得ず貸す場合は、「金額・期限・返済方法」をチャット履歴などで明確に記録し、「言った・言わない」の誤解を防ぐ。
- 断り方:「貸せない」意思を伝えつつ、「どうしたの?」と相談に乗り、お金以外の解決策(親に相談、公的機関の利用など)を一緒に考える。
- 最終手段:もし貸すなら、「返ってこない前提(あげるつもり)」で、自分のお小遣いの範囲内の金額にする。
「お金」は、人間関係を試すリトマス紙のようなものです。お金にルーズな関係は、いずれ友情そのものもルーズにしていきます。
もし今、あなたが友達とのお金の貸し借りがある(貸している、または借りている)状態なら、先延ばしにせず、すぐに状況を確認しましょう。
まずはチャット履歴やメモを見返し、金額や約束した期限がどうなっているかを確認してください。もし返済が滞っているなら、勇気を出して「あの件どうなってる?」と確認し、今後の返済について改めて話し合うことが、関係修復の第一歩です。

お金の貸し借りは、友情の「信用」を前借りしているのと同じです。信用を使い果たす前に、ルールを明確にし、健全な関係を築く努力をしましょう。それが本当の金融リテラシーです。
このページの内容の理解度をクイズでチェック!
免責事項
本記事は、一般的な企業・業界情報および公開資料等に基づく執筆者個人の見解をまとめたものであり、特定の銘柄や金融商品への投資を推奨・勧誘するものではありません。また、記事内で取り上げた見解・数値・将来予測は、執筆時点の情報に基づくものであり、その正確性・完全性を保証するものではありません。今後の市場環境や企業動向の変化により、内容が変更される可能性があります。
本記事に基づく投資判断は、読者ご自身の責任と判断において行ってください。 本記事の内容に起因して生じたいかなる損失・損害についても、当サイトおよび執筆者は一切の責任を負いません。本記事は金融商品取引法第37条に定める「投資助言」等には該当せず、登録金融商品取引業者による助言サービスではありません。