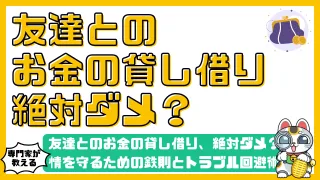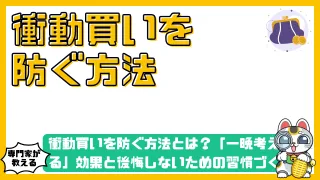本ページはプロモーションが含まれています。
このページの内容の理解度をクイズでチェック!
目次
はじめに
「今月もなぜかお金が残らない」「欲しいものを我慢しているつもりなのに、貯金が増えない」
高校生や社会人になったばかりの頃、こうしたお金の悩みを抱える人は少なくありません。アルバイトやお給料で手にしたお金を、計画的に使っているつもりでも、月末には残高が心もとなくなってしまう。その原因は、「なんとなく」お金を使っていることにあるかもしれません。
賢くお金と付き合い、将来のために貯蓄や投資を始める第一歩は、自分にとっての「支出のモノサシ」を持つことです。
この記事では、その最も基本的で強力なモノサシである「Needs(ニーズ=必要なもの)」と「Wants(ウォンツ=欲しいもの)」の違いについて、徹底的に解説します。この2つを明確に区別できるようになれば、あなたは日々の支出を自分でコントロールできるようになり、無駄遣いを減らし、本当に大切なことにお金を使えるようになります。

お金の使い方を学ぶことは、人生の選択肢を増やすための基礎体力づくりです。まずは自分のお金の「流れ」をWantsとNeedsという視点で把握することから始めましょう。
Needs(必要)とWants(欲しい):お金の使い方の基本ルール
お金を使う時、すべての支出は大きく分けて「Needs(必要)」と「Wants(欲しい)」の2種類に分類できます。この区別を理解することが、家計管理と賢い支出のスタートラインです。
Needs(ニーズ)とは?
Needs(ニーズ)とは、「生活に不可欠な支出」を指します。これらが満たされないと、健康的な生活を送ることが困難になったり、社会生活に支障が出たりするものです。いわば、生きていくための「土台」となる支出です。
- Needsの具体例
- 食費(最低限):生きていくために必要な、自炊を中心とした基本的な食材費。
- 住居費:家賃や住宅ローン、寮費など。
- 水道光熱費:電気、ガス、水道の料金。
- 通信費(最低限):社会生活や連絡に必要な最低限のスマートフォンやインターネットの料金。
- 日用品費:トイレットペーパーや洗剤など、生活必需品。
- 交通費:通勤や通学に必要な定期代やガソリン代。
Wants(ウォンツ)とは?
Wants(ウォンツ)とは、「なくても生活はできるが、あると生活がより豊かになる支出」を指します。これらは、心の満足度や生活の質(QOL=クオリティ・オブ・ライフ)を高めるためのものです。
- Wantsの具体例
- 趣味・娯楽費:旅行、映画鑑賞、ゲーム、スポーツ観戦など。
- 外食・嗜好品:友人とのランチ、カフェ代、お酒、お菓子など。
- 贅沢品:ブランド品のバッグ、高級な腕時計、必要以上のアクセサリー。
- 過度なファッション:流行を追うためだけの衣服費や、必要以上の数の靴。
- サブスクリプション:複数の動画配信サービスや、あまり利用しない定額サービス。
優先順位は「Needs」が絶対
この2つの支出において、最も重要なルールは「必ずNeedsをWantsより優先する」ことです。
家賃や光熱費といったNeedsの支払いを後回しにして、趣味や遊びといったWantsにお金を使ってしまえば、生活はすぐに立ち行かなくなります。お給料が入ったら、まずはその月に必要なNeedsの分を確実に取り分け(確保し)、残った予算の中でWantsをどう満たすか考える。この順番こそが、健全な家計の基本です。

Needsは「生存コスト」、Wantsは「楽しむコスト」と考えると分かりやすいです。まずは生存コストを確実に確保する。この鉄則を守るだけで、お金の不安は大きく減ります。
「必要」という名のワナ:必需品に潜む「隠れWants」
WantsとNeedsの区別が難しいのは、「これはNeeds(必要)だ」と思い込んでいる支出の中に、実はWants(欲しい)の要素が隠れているケースが多いからです。これを「隠れWants」と呼びます。
「必需品だから」と安心してしまうと、私たちはその中身を吟味することなく、無意識にWantsにお金を使いすぎてしまいます。
「食費」という名の落とし穴
例えば、「食費」は生きていくために不可欠なNeedsです。しかし、その中身はどうでしょうか。
- スーパーで買う基本的な食材(米、野菜、肉):Needs
- 毎日のように利用するコンビニの弁当や総菜:Wants(自炊より割高なため)
- 週に数回の高級レストランでのディナー:Wants
- なんとなく買ってしまう新作のお菓子や高級アイス:Wants
「食費」というNeedsの枠組みの中でも、「最低限必要なライン」を超えた部分はWantsの可能性があります。「必需品だからいくら使っても良い」という考え(※ありがちな誤解)は、家計を圧迫する大きな原因となります。
「交通費」や「通信費」にも注意
この「隠れWants」は、あらゆる費目に潜んでいます。
- 交通費
- 通勤・通学の電車賃(Needs)
- 「間に合うけど面倒だから」と乗るタクシー代(Wants)
- 通信費
- 連絡や情報収集に必要なスマホ基本料(Needs)
- 使いこなせていない大容量データプランや、最新機種への頻繁な買い替え(Wants)
- 被服費
- 季節に応じた最低限の衣服(Needs)
- 流行を追うためだけ、またはストレス解消で買う服(Wants)
大切なのは、「最低限必要なラインはどこか?」を自分なりに設定し、それを超えた部分を「Wants(贅沢)」として認識することです。

「これはNeedsだからOK」という思考停止が一番の敵です。「本当にその質、その量、その頻度が必要か?」と自問する癖をつけることが、「隠れWants」を見抜く鍵となります。
衝動買いを防ぐ!WantsとNeedsの具体的な見分け方
「これはWantsか、Needsか?」と迷った時、冷静に判断するための具体的なテクニックがあります。特に、一時的な感情に流されて買ってしまう「衝動買い」を防ぐのに有効です。
テクニック1:買う前に一呼吸おく(自問)
買い物をしようと思った瞬間、レジに持っていく前に、自分にこう問いかけてみましょう。
- 「これは、Wants? それとも Needs?」
- 「なぜ、今これが本当に必要なのか?」
- 「これを買わなかったら、具体的に何に困るのか?」
この質問に明確に答えられない場合、それはWantsである可能性が非常に高いです。衝動買いの多くは、「緊急で必要なNeedsだ」(※ありがちな誤解)と錯覚することで発生しますが、実際は一時的な感情によるWantsに過ぎません。
テクニック2:「冷却期間」を設ける(1週間ルール)
特に高額なものや、すぐに必要か判断がつかないWantsの場合、「1週間待ってみる」というルール(冷却期間)が非常に効果的です。
欲しいと思った瞬間は、感情が高ぶっています。しかし、その商品を一度棚に戻し、1週間(あるいは1日でも構いません)時間を置くことで、冷静さを取り戻すことができます。
- 1週間後も、まだ強く欲しいか?
- 1週間、それがなくても全く困らなかったのではないか?
一時的な欲求(Wants)であれば、時間が経てば熱が冷めることも多いです。この冷却期間を設ける習慣は、感情的な浪費を防ぐための強力な防衛策となります。
テクニック3:代用できるものはないか考える
「それが欲しい」のではなく、「その商品が解決してくれるコト(ニーズ)」に目を向けるのも一つの方法です。
- 例:喉が渇いた(Needs)
- 自販機で一番高いジュースを買う(Wants)
- スーパーで安い水を買う(Needsに近い)
- 持参した水筒のお茶を飲む(Needs)
- 家に帰るまで我慢する(Needs)
同じ「喉の渇きを潤す」というNeedsを満たすためでも、選択肢によってコストは大きく変わります。「自販機で一番高いジュースを選ぶ」という行動は、渇きを潤す(Needs)以上の、「好きな味を楽しみたい」「冷たくて甘いものが欲しい」というWantsを満たす行動と言えます。

「今すぐ欲しい!」という感情は、多くの場合「錯覚」です。その正体がWantsであることを見抜き、冷静に判断するための「自分ルール」を持つことが、衝動買いを防ぐ最も有効な手段です。
Wants(欲しい)は悪じゃない!賢い欲求との付き合い方
ここまでWantsを抑える話をしてきましたが、Wants(欲しいもの)は決して「悪」や「ムダ遣い」(※ありがちな誤解)ではありません。Wantsをすべて我慢する生活は、非常に窮屈でストレスが溜まります。
実際、「お金が貯まる人はWantsを一切買わない人だ」(※ありがちな誤解)というのも間違いです。賢くお金を貯めている人ほど、Wantsとの付き合い方が上手なのです。
Wantsがもたらすポジティブな効果
Wantsを満たすことには、重要な役割があります。
- 生活の質(QOL)の向上
趣味や旅行、美味しい食事は、人生に彩りを与え、満足度を高めます。 - モチベーションの維持
「あの服を買うために仕事を頑張ろう」「旅行に行くために節約しよう」といったWantsは、日々の努力の原動力(モチベーション)になります。 - 自己投資
Wantsの中には、将来の自分への「自己投資」となるものもあります。例えば、スキルアップのための書籍購入やセミナー参加は、短期的にはWantsに見えますが、長期的には収入アップ(Needsの安定化)につながる可能性があります。
重要なのは「優先順位」と「予算化」
Wantsをすべて我慢すると、そのストレスから反動で大きな浪費(どか食いや衝動的な高額消費)をしてしまう危険性すらあります。
大切なのは、「Needsを圧迫しない範囲で、Wantsに優先順位をつける」ことです。
- Needs予算を最優先で確保する
まず、家賃や食費などのNeedsにかかる費用を先に確保します。 - Wants用の予算枠を作る
残ったお金(可処分所得)から、貯蓄分を差し引き、残りを「Wantsに使っても良い予算」として設定します。 - Wantsに優先順位をつける
「今月一番欲しいもの」は何かを考え、優先度の高いものからその予算内で購入します。流行っているから、他人が持っているから(※ありがちな誤解)という理由ではなく、「自分が本当に満足できるか」という基準で選ぶことが重要です。

Wantsは「敵」ではなく「仲間」です。Needsという土台をしっかり固めた上で、Wantsを計画的に満たすこと。それが、我慢のストレスなく、楽しくお金を貯めていく秘訣です。
まとめ:WantsとNeedsの区別が、家計管理の第一歩
Wants(欲しい)とNeeds(必要)の区別は、感覚的なものではなく、家計管理における具体的な「技術」です。
この区別が曖昧なままでは、どれだけ収入が増えても、支出も同様に増えてしまい(パーキンソンの法則)、お金は一向に貯まりません。
自分だけの「モノサシ」を持つ
何がNeedsで、何がWantsかは、最終的には「自分の価値観」で定義するしかありません。
- 他人にとってはWantsでも、自分にとっては(例えば仕事で使うなら)Needsかもしれません。
- 逆に、他人がNeedsだと言っても、自分には不要なものもあります。
大切なのは、他人の基準(※ありがちな誤解)に流されず、自分にとっての「最低限必要なライン(Needs)」と「生活を豊かにするライン(Wants)」を明確に引くことです。
賢いお金の使い方=Wantsのコントロール
賢いお金の使い方の本質は、以下のサイクルを習慣化することです。
- Needs(必要)を確実に満たす。
- Needsの中の「隠れWants」を削る。
- 残った予算で、優先順位の高いWants(欲しい)を楽しむ。
この習慣こそが、日々の満足度を保ちつつ、将来のための貯蓄や投資にお金を回す余力を生み出すのです。

WantsとNeedsの区別は、家計簿をつけるよりも簡単で、即効性のある家計改善の第一歩です。この「モノサシ」を身につけ、自分のお金の流れをコントロールする力を手に入れましょう。
まとめとやるべきアクション
今回は、賢いお金の使い方と家計管理の基本である「Wants(欲しい)」と「Needs(必要)」の見分け方について解説しました。
- Needs:生活に不可欠な支出(家賃、最低限の食費など)
- Wants:生活を豊かにする支出(趣味、外食、贅沢品など)
- 優先順位:必ずNeedsを先に確保する。
- 注意点:必需品(Needs)の中にも「隠れWants」が潜んでいる。
- 見分け方:「1週間待つ」などの冷却期間を設ける。
- 付き合い方:Wantsは我慢せず、Needs予算を確保した上で、優先順位をつけて予算内で楽しむ。
この区別を意識するだけで、日々の買い物での選択が変わり、無駄遣いが自然と減っていきます。
まずは、この「Wants」と「Needs」のモノサシを実際に使ってみることから始めましょう。
【今日からできるアクション】
今週、自分が「Wants(欲しい)」で買ったもの(コンビニのコーヒー、お菓子、必要以上の外食など)を3つ書き出してみましょう。そして、「それがなくても本当に困らなかったか?」を冷静に振り返ってみてください。
この小さな振り返りが、あなたの「お金のクセ」に気づき、賢い消費者になるための第一歩となります。

WantsとNeedsの区別は、一度身につければ一生使える「お金のスキル」です。今日の買い物から早速、心の中で「これはWants? Needs?」と問いかける習慣を始めてみてください。
このページの内容の理解度をクイズでチェック!
免責事項
本記事は、一般的な企業・業界情報および公開資料等に基づく執筆者個人の見解をまとめたものであり、特定の銘柄や金融商品への投資を推奨・勧誘するものではありません。また、記事内で取り上げた見解・数値・将来予測は、執筆時点の情報に基づくものであり、その正確性・完全性を保証するものではありません。今後の市場環境や企業動向の変化により、内容が変更される可能性があります。
本記事に基づく投資判断は、読者ご自身の責任と判断において行ってください。 本記事の内容に起因して生じたいかなる損失・損害についても、当サイトおよび執筆者は一切の責任を負いません。本記事は金融商品取引法第37条に定める「投資助言」等には該当せず、登録金融商品取引業者による助言サービスではありません。