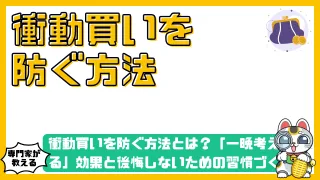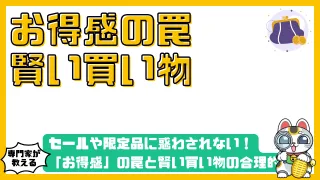本ページはプロモーションが含まれています。
このページの内容の理解度をクイズでチェック!
目次
はじめに
「友達グループで、自分だけ持っていない」
「SNSで流行っているから、なんとなく欲しい気がする」
「周りに合わせておかないと、話についていけないかも…」
高校生や新社会人になると、交友関係が広がり、新しいコミュニティに属する機会が増えます。それと同時に、こうした「周りの目」や「集団の空気」を意識してお金を使ってしまう場面も出てくるのではないでしょうか。
「みんなが持ってるから」という理由は、一見すると「それだけ人気なら良いものだろう」という合理的な判断のように思えます。しかし、その多くは「自分に本当に必要か」という問いよりも、「周りと同じであることの安心感」や「仲間外れになりたくない」という心理が優先されています。
この記事では、なぜ私たちが「みんな」に流されてしまうのか、その正体である「同調圧力」について解説します。そして、他人基準の「見栄」による支出から抜け出し、自分自身の「価値観」に基づいた、本当に満足度の高いお金の使い方を見つける方法を探っていきます。

「みんな」と同じであることに安心するのは自然な心理です。でも、その「みんな」とは誰なのか、一度立ち止まって考えることが大切です。
「みんな」という同調圧力の正体
私たちはなぜ、「みんなが持ってる」という言葉にこれほど弱いのでしょうか。
その背景には、「同調圧力(どうちょうあつりょく)」と呼ばれる心理が働いています。同調圧力とは、特定の集団の中で、少数派の意見や行動が、多数派の意見や行動に合わせるように誘導される、目には見えない力(圧力)のことです。
「孤立」を恐れる人間の本能
人間は社会的な生き物であり、本能的に「集団に所属していたい」という欲求を持っています。集団から孤立することは、大昔の人間にとっては「死」を意味することもありました。その名残から、私たちは無意識のうちに「集団から孤立することへの恐れ」を抱えています。
「みんなと違う行動をとる」ことは、この恐れを刺激します。「あの人、変わってる」「空気が読めない」と思われたくない。その結果、本心ではそれほど必要性を感じていなくても、「みんなが持っている」という理由だけで、周囲と同じ行動をとることで安心感を得ようとするのです。
その「みんな」とは、一体誰?
ここで冷静に考えてみたいのが、「みんなが持ってる」という時の「みんな」の定義は非常に曖昧である、という事実です。
- クラスメイトのAさんとBさんが持っていただけかもしれない。
- SNSのタイムラインで、たまたま3回連続で見かけただけかもしれない。
- 「今、流行ってますよ」という店員さんのセールストークかもしれない。
実際には「全員」ではなく、ごく一部の人が持っているだけだとしても、私たちの脳は「自分も持たなければ」とその小さな集団への同調を始めてしまいます。
購入する理由が「それが必要だから」ではなく、「みんなが持っているから」にすり替わっていないか。まずは、その「みんな」という言葉の呪縛に気づくことが重要です。

同調圧力は、特に集団生活が長い日本では強く働きがちです。その存在を「知る」ことが、流されないための第一歩になります。
見栄と満足度のコスト。なぜ「他人軸」の買い物は満たされないのか
同調圧力や「見栄(みえ)」、つまり他人によく見られたいという気持ちから買い物をすると、何が起こるでしょうか。
確かに、流行のアイテムを手に入れた瞬間は「仲間に入れた」「これで恥ずかしくない」という一時的な満足感や安心感が得られるかもしれません。
しかし、その満足は長続きしないことが多いのです。
お金を使ったのに、心が満たされない理由
同調圧力や見栄による支出がもたらす最大の問題点は、「自分の価値観に合っておらず、長期的な満足度が低いこと」です。
それは、買い物の判断基準が「私」ではなく「他人」にある、「他人軸」での買い物だからです。
- 「Aさんから『センスいいね』と思われたいから」
- 「グループで浮かないように、とりあえず同じブランドで揃えよう」
- 「この価格帯のものを持っていないと、下に見られそうだから」
こうした動機で選んだものは、本当に自分が心から「好き」なものや「必要」なものではありません。そのため、手に入れた瞬間の高揚感が過ぎ去ると、「なぜこれにお金を使ったんだろう」「思ったほど嬉しくないな…」という虚しさや後悔が残りがちです。
予算以上の支出という金銭的コスト
さらに深刻なのは、金銭的なコストです。「他人軸」で買い物を始めると、自分の予算や経済状況を無視した支出につながりやすくなります。
- 「友達はみんな海外旅行に行っているから、自分もローンを組んで行かないと」
- 「先輩が高価な時計をしていたから、自分も無理して買わないと示しがつかない」
このように、他人との比較や見栄がエスカレートすると、予算以上の支出リスクが格段に高まります。お金を使った割に心が満たされず、それどころか将来のための貯蓄や投資に回すべきお金まで失ってしまう、という二重の損失を被ることになるのです。

他人からの評価のためにお金を使うと、いくら使っても心は満たされません。お金の満足度は、金額ではなく「自分の価値観に合っているか」で決まります。
自分の「価値観」の見つけ方。「自分軸」という判断基準を持つ
では、どうすれば同調圧力や見栄に流されず、満足度の高いお金の使い方ができるのでしょうか。
その答えは、他人軸の対極にある「自分軸」を持つこと。つまり、自分自身の「価値観(何を大切にするか)」を明確にすることです。
自分の価値観がはっきりしていれば、周りが何を持っていても、「自分にはこれが必要だ」「自分はこっちの方が好きだ」と、自信を持って判断できるようになります。
価値観を明確にする3つのステップ
とはいえ、「あなたの価値観は?」と聞かれても、すぐに答えられないかもしれません。価値観を見つけるには、少し練習が必要です。
- 自分が何に喜びを感じるか知る
まずは、過去を振り返ってみましょう。最近、お金を使ったことで「本当に嬉しかった」「心から満足した」と感じた経験は何ですか?
(例:友達と美味しいものを食べた経験、欲しかった本を買って知識を得たこと、趣味の道具を揃えたこと)
逆に、「お金を使ったのに後悔した」経験も書き出してみます。 - お金を使う優先順位を決める
書き出した「喜び」を眺めて、自分が何にお金を使いたいのか、優先順位をつけてみます。
(例:1位「経験(旅行や食事)」、2位「学び(書籍やスクール)」、3位「健康(ジムや質の良い食事)」、4位「ファッション」…など) - 判断基準を書き出してみる
優先順位が見えてきたら、「自分はこういうものにお金を使う」「こういうものには使わない」という、自分なりの判断基準(マイルール)を言葉にしてみましょう。これがあなたの「価値観」の土台となります。
ケーススタディ:友人が「みんな」に流されそうだったら?
もし、あなたの友人が「みんなが持ってるから」という理由で、高額なスニーカーを買おうとしていたら、どうアドバイスしますか?
- A. 「そんなもの買うなんて無駄だ」と強く否定する。
- B. 「自分も同じものを買う」と一緒に購入する。
- C. 「流行ってるから買った方がいい」と背中を押す。
- D. 「本当に欲しいか、一晩考えてみたら?」と促す。
ここで最も建設的なのは、Dの選択肢です。
Aのように頭ごなしに否定するのは、相手の価値観を否定することになり、関係が悪化するかもしれません。BやCは、相手の同調圧力にあなたまで巻き込まれてしまっています。
Dのアドバイスは、前回の記事(衝動買いと時間の効果)とも通じますが、この場合のポイントは「時間」を与えることです。「みんな」という言葉で高ぶっている感情を一度リセットさせ、「同調圧力」に気づき、「本当に自分の価値観(=欲しい)に合っているか」を冷静に判断する時間を与える。
これが、本人の価値観を尊重しつつ、後悔する可能性を減らすための、最も優しいアドバイスと言えるでしょう。

自分の価値観が分からない、という人も焦る必要はありません。日々の小さな「好き」や「楽しい」をメモすることから始めてみましょう。
SNSと「見せかけの必要」。その「欲しい」は本物か?
「みんなが持っている」という同調圧力を、現代において最も強力に増幅させているのが「SNS」です。
InstagramやX(旧Twitter)、TikTokなどのタイムラインには、インフルエンサーのおすすめ商品、友人たちの楽しそうな旅行や食事の写真(いわゆる「リア充」な投稿)がひっきりなしに流れてきます。
SNSが「必要」を錯覚させるメカニズム
私たちはSNSによって、常に他人と比較しやすい環境に置かれています。
他人の「演出された生活」のハイライト(最も良く見せたい部分)を日常的に見続けることで、それが世の中の「普通」であり、自分もそうあるべきだ(それを持っていないと「必要」だ)と錯覚しやすくなるのです。
- 「いいね」が欲しいための消費
「これを買えば、SNSで『いいね』がたくさんもらえるかも」という動機が、本来の必要性を上回ってしまうことがあります。 - 広告と個人の投稿の境界が曖昧
インフルエンサーの投稿が、純粋なおすすめ(個人の感想)なのか、企業からお金をもらった広告(PR)なのか、見分けがつきにくいケースが増えています。私たちは、広告だと気づかないうちに「流行っている」と刷り込まれている可能性があるのです。
SNSで「欲しい」と感じたら?
もしSNSを見て「このバッグが必要だ」「このカフェに行かなくては」と強く感じた時、購入ボタンを押したり、店を予約したりする前に、まず立ち止まって疑うべきことがあります。
それは、「それは自分の本当の価値観か、それともSNS上の見栄か?」という問いです。
「このバッグが欲しいのは、機能性やデザインが自分の価値観に合っているからか? それとも、あのインフルエンサーと同じものを持ちたいという『見栄』や『憧れ』だけではないか?」
SNSで見るものは、あくまで他人の生活の一部であり、多くの場合、良く見せるために演出(フィルター)がかかっています。その「見せかけの必要」と、「自分の現実の生活」を区別する冷静な視点が、今、強く求められています。

SNSは「世界のショーウィンドウ」のようなもの。素敵なものが並んでいますが、すべてが自分に必要なわけではありません。窓の向こう側と自分の生活は別物です。
「自分軸」で選ぶ満足。お金の使い方で「私」を表現する
これまで見てきたように、「みんな」という同調圧力や「見栄」に流されてお金を使うと、一時的な安心感は得られても、長期的な満足は得られません。
お金の満足度を高めるただ一つの鍵は、判断の主語を「みんな」から「私」へと取り戻すこと。すなわち、他人の基準ではなく、自分の基準(=価値観)で選ぶことです。
自分の価値観に基づいたお金の使い方とは?
自分の価値観に基づいてお金を使うとは、具体的にどういうことでしょうか。それは、次のような行動に現れます。
- 周囲が持っていなくても、自分が必要(価値がある)と判断すれば買う。
(例:みんなは流行の服を買っていても、自分は趣味の本や学びたい講座にお金を使う) - いくら流行していても、自分が必要ない(価値観に合わない)と判断すれば買わない。
(例:みんなが高級ブランドのバッグを持っていても、自分は機能的でシンプルなバッグで満足しているので買わない)
大切なのは、長期的な満足度を優先することです。その場の「見栄」や「安心感」のために浪費するのではなく、自分の価値観に沿った「投資」や「経験」にお金を使うことで、その満足は長く続き、自分自身の資産となります。
「買わない選択」を尊重する
「自分軸」で選ぶことは、「買わない選択」も尊重することです。
周りが盛り上がっている中で「自分は要らない」と言うのは、少し勇気がいるかもしれません。しかし、それはワガママでもケチでもなく、あなたが自分の価値観を大切にしている証拠です。
同調圧力に気づき、他人の目を気にしすぎることなく、自分の価値観(自分軸)に基づいてお金を使う。それが、見栄や後悔から解放され、あなたらしい豊かな生活を送るための、最も確実な第一歩となります。

「自分軸」を持つとは、ワガママになることではありません。自分の価値観を大切にし、他人の価値観も尊重すること。お金の使い方は、その練習に最適です。
まとめとやるべきアクション
今回は、「みんなが持ってるから」という理由で買い物をすることの裏にある「同調圧力」や「見栄」の心理、そしてそれに流されないための「自分軸(価値観)」の見つけ方について解説しました。
「みんな」という曖昧な基準に合わせるのではなく、「私」が本当に必要か、何を大切にしたいかで判断する。それが、お金に振り回されず、満足度の高い使い方をするための鍵です。
SNSなどで他人の華やかな生活が目に入りやすい時代だからこそ、自分の価値観という「軸」をしっかり持つことが、自分らしい豊かさを築く上で何よりも重要になります。
最初の一歩を踏み出そう
この記事で学んだことを、ぜひあなたの生活で実践してみてください。
まずは、自分自身の「価値観」と向き合う、このアクションから始めてみましょう。
最近「みんなが持ってるから」という理由で欲しくなったものを1つ挙げ、それが本当に自分の価値観に合っているか(なぜ必要なのか)を書き出してみましょう。
- 「(例)〇〇社のワイヤレスイヤホン。理由は、友達がみんな持っていて、自分だけ有線なのが恥ずかしいから。」
→ 本当に必要か?:「音質にこだわりはないし、今のイヤホンでも困っていない。恥ずかしい、という『見栄』が理由かもしれない。」
このように、自分の「欲しい」の裏にある動機を分析することで、それが「同調圧力」なのか、それとも「本当に必要なもの」なのかが見えてくるはずです。

「みんな」ではなく「私」を主語にしてお金と向き合うこと。それが、後悔しない使い方と、自分らしい豊かさにつながっていきます。
このページの内容の理解度をクイズでチェック!
免責事項
本記事は、一般的な企業・業界情報および公開資料等に基づく執筆者個人の見解をまとめたものであり、特定の銘柄や金融商品への投資を推奨・勧誘するものではありません。また、記事内で取り上げた見解・数値・将来予測は、執筆時点の情報に基づくものであり、その正確性・完全性を保証するものではありません。今後の市場環境や企業動向の変化により、内容が変更される可能性があります。
本記事に基づく投資判断は、読者ご自身の責任と判断において行ってください。 本記事の内容に起因して生じたいかなる損失・損害についても、当サイトおよび執筆者は一切の責任を負いません。本記事は金融商品取引法第37条に定める「投資助言」等には該当せず、登録金融商品取引業者による助言サービスではありません。