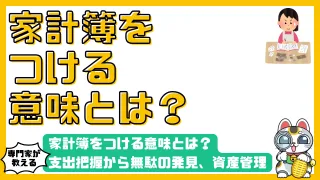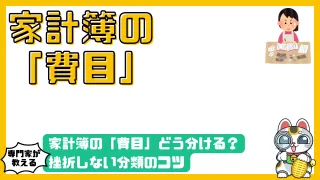本ページはプロモーションが含まれています。
このページの内容の理解度をクイズでチェック!
目次
はじめに
「貯金がなかなかできない」「毎月何にお金を使っているか分からない」。そんな悩みを抱えている高校生や新社会人の皆さんにとって、強力な味方となるのが「家計簿」です。家計簿と聞くと「面倒くさい」「細かくつけないといけない」といったイメージがあるかもしれません。
しかし、家計簿の本質は、自分のお金の使い方を理解し、より良い未来のためにお金をコントロールする技術を学ぶことにあります。難しく考える必要はありません。家計簿の活用は、たった3つの基本的なステップを繰り返すことで成り立っています。
それは「記録」「集計」「反省(見直し)」の3ステップです。
この記事では、家計簿をこれから始めたい人、または一度挑戦して挫折してしまった人に向けて、家計簿活用の基本的なサイクルと、無理なく続けるためのコツを詳しく解説します。この基本サイクルを学ぶことで、あなたも「お金が貯まる仕組み」を自分で作れるようになります。

家計簿は「お金の健康診断」のようなものです。まずは自分の現状を知ることから、未来のための資産管理が始まります。
家計簿の第一歩「記録」:お金の動きを把握する
家計簿のすべての始まりは、日々の「お金の動き」を記録することです。いつ、何に、いくら使ったか(支出)、そして、いつ、いくら入ったか(収入)を具体的に把握します。
これがなければ、家計の現状分析は始まりません。しかし、多くの人がこの「記録」の段階で完璧を目指しすぎて挫折してしまいます。
大切なのは、1円単位で完璧に記録することではなく、まずは「続けること」です。最初は8割程度の精度でも構いません。自分のお金が動いたという事実を掴む習慣をつけることが最優先です。
自分に合った記録方法を選ぶ
記録方法は一つではありません。自分にとって最もストレスの少ない方法を選びましょう。
- 家計簿アプリ: スマートフォンで手軽に入力でき、レシートを撮影するだけで自動的に品目を読み取ってくれる機能や、銀行口座・クレジットカードと連携して利用履歴を自動で取り込む機能(API連携など)があるものも多いです。手軽さを重視する人に向いています。
- 表計算ソフト(Excel、Googleスプレッドシートなど): 自分で好きなように項目(費目)を設定したり、グラフを作成したりと、カスタマイズ性が高いのが特徴です。パソコンでの作業が得意な人に向いています。
- ノート(手書き): 手で書くことで支出の記憶が定着しやすいというメリットがあります。また、自分のペースで自由に書き込める良さもあります。
どれを選んでも構いませんが、まずは「これなら続けられそう」と思えるものを選んでみてください。
記録漏れしやすい支出に注意
特に忘れがちなのが、少額の決済や現金以外の支払いです。
- 交通系ICカード(Suica, PASMOなど)での支払い: 電車代だけでなく、コンビニや自動販売機での少額決済も見落としがちです。利用履歴を定期的に確認する(駅の券売機やアプリなど)習慣をつけましょう。
- QRコード決済や電子マネー: ポイント還元などもあり利用機会が増えていますが、手軽な反面、使った感覚が薄れがちです。アプリの利用履歴をこまめにチェックしましょう。
- 自動販売機や割り勘での現金支出: レシートが出ない支出は、すぐにメモを取るか、スマートフォンのメモアプリに入力する癖をつけることが有効です。
まずは「レシートをすべて受け取り、一日の終わりにまとめて入力する(または撮影する)」というルールを決めるだけでも、記録の習慣化に役立ちます。

記録の段階で挫折する人が最も多いです。完璧を目指さず「まずは1週間」と決めて、簡単な方法でスタートしてみましょう。
家計簿の第二ステップ「集計」:お金の流れを可視化する
「記録」が日々のデータを貯める作業だとすれば、次のステップ「集計」は、貯めたデータを整理・分析して意味のある情報に変える作業です。
記録したデータを「集計」することで、漠然としていたお金の流れを可視化(目に見える形に)します。これが集計の最も重要な目的です。
「記録」だけを続けても、「今月は使いすぎたかも」という曖昧な感覚しか得られません。しかし、「集計」を行うことで、「何に」「いくら」使っているのかが具体的な数値として明確になります。
集計は、1週間ごと、あるいは1ヶ月ごとなど、期間を区切って行います。
集計の具体的な方法
集計作業は、主に以下の3つのステップで行います。
- 費目(カテゴリ)別に支出を分類する:
記録した支出を、「食費」「交通費」「日用品」「趣味・娯楽」「交際費」「住居費」「水道光熱費」「通信費」といった「費目」ごとに分類し、それぞれの合計金額を計算します。
(※家計簿アプリや表計算ソフトを使えば、この作業は自動または半自動で行えます。)
ここで注意したいのは、最初から費目を細かく分けすぎないことです。例えば「食費」を「外食」「自炊(食材)」「カフェ」などに細分化しすぎると、分類が面倒になり挫折の原因になります。まずは大きな分類で把握することから始めましょう。 - 収入と支出の合計を計算し、収支(差額)を出す:
その月の収入の合計額と、支出の合計額を計算します。そして「収入 − 支出」で、その月の収支(黒字か赤字か)を算出します。この数値が、あなたがその月にどれだけ貯金できたか(あるいは取り崩したか)を示す、最も重要な結果となります。 - グラフ化すると支出の割合が分かりやすい:
集計した費目別の支出額を、円グラフや棒グラフにしてみましょう。 支出全体のうち、どの費目がどれくらいの割合を占めているのかが一目でわかります。「食費が全体の30%も占めている」といった具体的な状況把握に役立ちます。
「集計は面倒だからやらなくてもいい」と考える人もいますが、これは大きな誤解です。集計をしなければ、記録したデータはただの数字の羅列で終わってしまいます。お金の流れを把握してこそ、次の「反省(改善)」につなげることができるのです。

記録が「点」なら、集計は「線」や「面」で流れを見ることです。この「可視化」こそが、家計簿の真価を発揮する第一歩です。
家計簿の第三ステップ「反省」:次の行動改善につなげる
家計簿の3つのステップの最後は「反省(見直し)」です。集計結果という「現実」を見て、お金の使い方を振り返り、改善点を見つけるプロセスです。
ここで重要なのは、「反省」とは、単に「使いすぎた…」と後悔したり、自分を責めたりすることではない、ということです。それは「ありがちな誤解」の一つです。
家計簿における「反省」とは、集計データに基づいた冷静な「分析」であり、次の行動をより良くするための前向きなステップです。
「反省」で行うべきこと
集計結果が出たら、以下の視点で振り返りを行います。
- 予算(計画)と実績(集計結果)を比較する:
もし事前に「今月の食費は3万円」といった予算(計画)を立てていた場合、集計結果(実績)とを比較します。予算内に収まったか、それともオーバーしてしまったかを確認します。 - 「なぜ使いすぎたか」具体的な理由を考える:
もし予算をオーバーしていた場合、その原因を具体的に分析します。これが「反省」ステップで最も重要な行動です。
例えば、「食費が予算オーバーした」という結果に対し、「自分を責める」のではなく、- 「急な飲み会が3回も入ったから(交際費の増加)」
- 「仕事が忙しく、外食やコンビニ弁当が多かったから(自炊の減少)」
- 「ストレスでつい高価なスイーツを買ってしまったから(浪費)」
といった具体的な理由を突き止めます。理由がわからなければ、対策も立てられません。
- 削減できそうな支出(ムダ遣い)を見つける:
支出を「消費(生活に必要なもの)」「浪費(ムダ遣い)」「投資(将来の自分に役立つもの)」の3つに分類して考えてみるのも有効です。特に「浪費」にあたる支出や、「今月はなくてもよかったな」と思う支出がなかったかを探します。
予算オーバー時に「とにかく翌月の予算を減らす」という行動を取りがちですが、原因を分析しないまま無理な予算を立てても、守れずに再び挫折するだけです。まずは冷静に「なぜ」を深掘りすることから始めましょう。

「反省」は「後悔」とは違います。データに基づいた冷静な「分析」こそが、具体的な「改善」アクションを生み出します。
家計簿を回す「活用サイクル」:PDCAで資産形成
家計簿は、「記録・集計・反省」の3ステップを一度やったら終わり、ではありません。この3ステップを繰り返し回し続けることで、家計は着実に改善していきます。
このサイクルは、ビジネスの現場などで使われる「PDCAサイクル」という考え方と非常によく似ています。
- P (Plan):計画
- D (Do):実行
- C (Check):検証(評価)
- A (Act):改善
これを家計簿に当てはめてみましょう。
- P (Plan):計画
「ステップ3:反省」で見つかった課題(例:外食が多かった)に基づき、「次の行動計画(予算)」を立てます。「来月は外食を週1回までにして、食費の予算を3万円に設定しよう」といった具合です。 - D (Do):実行
立てた計画(予算)を守るように意識しながら、日々の生活を送り、お金を使います。そして、その支出を「ステップ1:記録」していきます。 - C (Check):検証(評価)
月の終わり(または週の終わり)に、「ステップ2:集計」を行います。そして、立てた計画(予算)と、実際の結果(集計)を比較・検証します。これがPDCAの「C (Check)」にあたる、非常に重要なプロセスです。 - A (Act):改善
「ステップ3:反省」を行います。計画通りいったか、いかなかった場合はなぜか、を分析します。そして、「予算設定が厳しすぎたから、もう少し現実に合わせよう」「この節約方法はうまくいったから続けよう」といった「改善」策を考え、次の「P (Plan)=計画」に活かします。
このように、家計簿とは「P(予算立て)→ D(支出・記録)→ C(集計・比較)→ A(反省・分析)」というサイクルを回し続けるためのツールなのです。
この小さな改善のサイクルを回し続けることが、将来の貯金や資産形成という大きな成果につながる土台となります。

家計簿は「つけて終わり」では意味がありません。PDCAサイクルを回し、小さくても改善を続ける「習慣」にすることがゴールです。
家計簿を「続けるコツ」:挫折しないための心構え
多くの人が家計簿に挫折してしまう最大の理由は、「完璧を目指しすぎている」ことです。
「1円単位で収支が合わないと気持ち悪い」「毎日必ず記録しないといけない」といった完璧主義は、家計簿を続ける上で最大の敵となります。
家計簿の真の目的を思い出してください。それは「記録を完璧に取ること」ではなく、「収支を把握し、お金の使い方を改善すること」です。記録はあくまでそのための手段にすぎません。「記録さえすれば節約できるはず」というのも誤解で、記録した後の「集計」と「反省」がなければ、行動は変わりません。
家計簿を長く続けるためには、完璧主義を捨て、「8割できれば良し」とするくらいの気軽なマインドが鍵となります。
挫折しないための3つのヒント
- 1円単位のズレを気にしすぎない
数百円程度の誤差や「使途不明金」が出ても、深追いしないこと。全体の支出の傾向が把握できれば十分です。そのズレを探す時間に、もっと有意義なことができます。 - 忙しい時期は記録を休んでもよい
仕事や勉強が忙しくて記録ができなかった日があっても、自分を責めないでください。レシートさえ残しておけば、週末にまとめて入力することも可能です。数日休んでも、また再開すれば良いのです。 - 改善できた(貯金できた)成果を可視化する
家計簿をつけた結果、「今月は5,000円多く貯金できた」「浪費がこれだけ減った」といった成果が出たら、それを目に見える形で確認しましょう。通帳の残高が増えていくのを見るのも良いでしょう。小さな成功体験が、次も頑張ろうというモチベーションにつながります。
家計簿は、あなたを縛り付けるためのものではなく、あなたがより自由に、賢くお金と付き合っていくためのパートナーです。ぜひ気負わずに、できるところから始めてみてください。

家計簿の目的は「貯金をすること」や「使い方を改善すること」です。記録はあくまで手段。手段が目的化しないよう、気軽に取り組みましょう。
まとめとやるべきアクション
今回は、家計簿活用の基本である「記録・集計・反省」の3つのステップと、それを回し続けるPDCAサイクル、そして挫折しないためのコツについて解説しました。
- ステップ1:記録
まずは続けることを目標に、自分に合った方法で日々の収支を把握します。 - ステップ2:集計
記録したデータを費目別にまとめ、お金の流れを「可視化」します。 - ステップ3:反省
集計結果(現実)と予算(理想)を比べ、原因を「分析」し、次の改善につなげます。 - 継続のコツ
完璧を目指さず、8割できればOKというマインドで、手段(記録)が目的化しないように注意します。
家計簿を始めるのに、遅すぎることはありません。まずは最初の一歩を踏み出してみましょう。
【最初のアクション提案】
いきなり1ヶ月分をつけようと意気込む必要はありません。
まずは今から1週間、買い物をした際にもらったレシートをすべて保管してみてください。
そして、週末にそのレシートを見ながら、「食費」「日用品」「趣味」など大まかな分類で構わないので、合計金額を計算(集計)してみましょう。
たった1週間でも、あなたが「何に」お金を使っているかの傾向が、きっと見えてくるはずです。

まずは今週末、この1週間のレシートを集めてみてください。そこから見える小さな発見が、あなたの家計を変える大きな一歩になります。
このページの内容の理解度をクイズでチェック!
免責事項
本記事は、一般的な企業・業界情報および公開資料等に基づく執筆者個人の見解をまとめたものであり、特定の銘柄や金融商品への投資を推奨・勧誘するものではありません。また、記事内で取り上げた見解・数値・将来予測は、執筆時点の情報に基づくものであり、その正確性・完全性を保証するものではありません。今後の市場環境や企業動向の変化により、内容が変更される可能性があります。
本記事に基づく投資判断は、読者ご自身の責任と判断において行ってください。 本記事の内容に起因して生じたいかなる損失・損害についても、当サイトおよび執筆者は一切の責任を負いません。本記事は金融商品取引法第37条に定める「投資助言」等には該当せず、登録金融商品取引業者による助言サービスではありません。