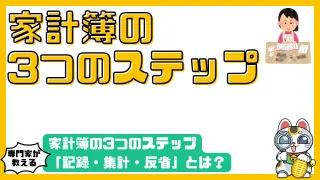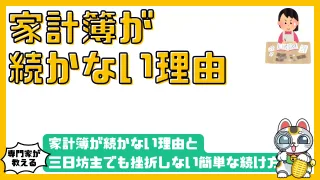本ページはプロモーションが含まれています。
このページの内容の理解度をクイズでチェック!
目次
はじめに
「今年こそ貯金をしよう」と決意して家計簿をつけ始めたものの、「この支出はどのカテゴリに入れたらいいんだろう?」「食費と雑費の境界線がわからない…」と悩み、最初の1週間で面倒になってやめてしまった。そんな経験はありませんか?
高校生や新社会人の皆さんが家計管理を始めようとするとき、最初にして最大のハードルが、この「費目(ひもく)分け」です。
家計簿と聞くと「面倒くさい」「細かくつけないと意味がない」というイメージが先行しがちですが、それは大きな誤解です。家計簿の本質は、自分のお金の流れを把握し、将来の夢(例えば、留学、一人暮らし、好きな趣味への投資など)を実現するために「お金をコントロールする力」を養うことにあります。
そのコントロールの第一歩が、まさに「費目分け」なのです。なぜなら、自分が「何に」「いくら」使っているかを正しく分類・把握できなければ、どこを節約し、どこにお金を振り分けるべきかの「作戦」が立てられないからです。
しかし、多くの人がこのスタートラインで、完璧を目指しすぎて挫折してしまいます。
この記事では、家計簿初心者の方や、過去に費目分けで挫折してしまった方に向けて、継続しやすい費目の分け方の基本から、無理なく管理できる「ざっくり管理」の具体的なコツまで、網羅的に解説します。
この記事を読めば、あなたも「面倒な作業」としての家計簿から卒業し、「未来をデザインするツール」として家計簿を活用できるようになるはずです。

費目分けは、家計という名の「地図」を作る作業です。完璧な地図を目指すより、まずは自分が迷子にならない程度の「大まかな地図」を完成させ、続けることが何より大切ですよ。
費目とは?家計簿における分類の基本
そもそも「費目(ひもく)」とは何でしょうか。
費目とは、家計簿をつける際に、支出の内容を分類するために使うカテゴリ(項目名)のことを指します。
皆さんが日々の生活で使っているお金には、すべて使い道があります。例えば、
- コンビニで買ったお弁当や飲み物
- 学校や会社へ行くための電車代
- 毎月支払うスマートフォンの料金
- 友人と楽しむ映画やカラオケの代金
これらの支出を、共通の性質でグループ分けしたものが「費目」です。
【代表的な費目の例】
- 食費: スーパーでの食材購入、外食、カフェ代、コンビニでのお弁当など。
- 交通費: 電車代、バス代、タクシー代、ガソリン代など。
- 住居費: (一人暮らしの場合)家賃、管理費、住宅ローン返済など。
- 水道光熱費: 電気代、ガス代、水道代。
- 通信費: スマートフォン代、自宅のインターネット回線費など。
- 日用品費: 洗剤、トイレットペーパー、シャンプーなど生活必需品。
- 交際費: 友人との食事代、プレゼント代、飲み会代など。
- 趣味・娯楽: 書籍、映画、音楽、旅行、習い事の月謝など。
- 医療費: 病院の診察代、薬代。
- 美容費: 化粧品、美容院代。
なぜ費目分けが不可欠なのか
「なぜ、使った金額を記録するだけではダメなの?」と思うかもしれません。
もし費目分けをせず、「1日に使った合計金額」だけを記録していたらどうなるでしょうか。月末に「今月は5万円も使ってしまった」という事実はわかっても、「なぜ5万円も使ったのか」「何に使いすぎたのか」が全く分かりません。これでは、来月の対策を立てようがありません。
一方で、費目分けをしっかり行い「集計(合計を出すこと)」をすると、お金の流れが明確に「可視化」されます。
【集計結果の例】
「今月の支出は5万円だった。その内訳は…」
- 食費: 25,000円
- 交際費: 10,000円
- 趣味・娯楽: 8,000円
- 交通費: 3,000円
- 日用品費: 4,000円
ここまで分かれば、「思ったより食費(特に外食)が多いな」「交際費は予算内だけど、趣味にお金を使いすぎたかもしれない」といった具体的な「反省(見直し)」が可能になります。
家計簿は「記録・集計・反省」の3ステップで成り立っていますが、費目分けは、この「集計」と「反省」の質を決定づける、非常に重要な土台作業なのです。

費目とは、お金の使い道に付ける「名前」です。この名前ごとに集計することで、初めて自分のお金の使い方を客観的に分析できるようになります。
なぜ費目分けで挫折する?初心者が陥る注意点
費目分けの重要性は理解していても、実際に多くの人が「面倒くさい」「続かない」と感じてしまいます。家計簿初心者が挫折するパターンには、いくつかの共通した「ありがちな誤解」が存在します。
誤解1:「費目は細かければ細かいほど良い」
これは最大の落とし穴です。「費目は細かければ細かいほど、正確に家計を把握できるはずだ」と考え、最初から完璧な分類を目指してしまうケースです。
例えば、「食費」という一つの費目を、
- 食材(スーパー)
- 外食(昼)
- 外食(夜)
- カフェ代
- 飲み会代
- お菓子・ジュース代
…というように、最初から10種類近くに細分化してしまうとどうなるでしょうか。
友人とランチをして、その後カフェでお茶をした場合、「これは外食(昼)とカフェ代に分けて…」と、支出が発生するたびに分類に悩むことになります。スーパーで食材とお菓子を買ったレシートを見ながら、「これは食材、こっちはお菓子…」と仕分ける作業は、想像以上に記録(仕分け)が面倒になります。
この「面倒くささ」が積み重なると、やがて家計簿をつけること自体が苦痛になり、「もういいや」と挫折してしまうのです。
誤解2:「すべての支出を完璧に分類すべきだ」
誤解1とも関連しますが、「1円単位で完璧に仕分けなければならない」という完璧主義も挫折の原因です。
例えば、コンビニで雑誌とパンを買った場合、「これは趣味・娯楽費と食費に分けないと…」と悩み、レシートのない自動販売機のジュース代(130円)を記録し忘れたことに気づいて「もう正確じゃないから意味がない」と投げ出してしまうパターンです。
家計簿の目的は、会計士のような正確な帳簿を作ることではありません。大まかな「お金の流れの傾向」を掴むことです。100円や200円のズレよりも、記録が止まってしまうことのほうが大きな問題です。
誤解3:「他人の家計簿の費目を真似すればよい」
SNSや雑誌で見かける「理想の家計簿」の費目分けを、そのまま自分に当てはめようとするのも危険です。
人によって、ライフスタイルは全く異なります。
- 実家暮らしの学生: 「住居費」や「水道光熱費」はかからない代わりに、「お小遣い」や「アルバイト代」の範囲で「交際費」や「趣味・娯楽」を管理するのがメインかもしれません。
- 一人暮らしの新社会人: 「家賃」や「光熱費」といった「固定費」の管理が必須になります。
- 趣味にお金をかけたい人: 「趣味・娯楽」費をあえて細かく分けて管理したいかもしれません。
他人の基準を無理に真似ても、自分の実態と合わなければ分類がストレスになるだけです。「他人は他人、自分は自分」という割り切りが重要です。

家計簿は「誰かに見せるため」ではなく「自分のため」につけるもの。完璧主義や他人との比較は、継続の最大の敵です。まずは「自分にとって楽かどうか」を基準にしましょう。
継続しやすい費目分けのコツ「ざっくり管理」
家計簿を継続させる最大のコツは、完璧を目指すことではなく、自分にとって管理しやすい「ざっくり管理」のルールを見つけ、習慣化することです。
「ざっくり」と聞くと「適当でいい加減」というイメージを持つかもしれませんが、ここでいう「ざっくり管理」とは、「継続するために、あえて管理のハードルを下げる」という戦略的なアプローチです。
特に初心者の方は、できるだけシンプルな分類から始めることを強くおすすめします。
方法1:最強の分類「固定費」と「変動費」で分ける
家計簿初心者にとって、まず最初に取り組むべき最もシンプルで強力な分類が、支出を大きく「固定費」と「変動費」の2種類に分ける方法です。
- 固定費 (Kotei-hi):
毎月(または毎年)ほぼ一定額が自動的に出ていく支出。一度契約すると、金額を(節約)するのが難しい支出とも言えます。
(例) 家賃、管理費、水道光熱費の「基本料金」、通信費(スマホ・ネット)、保険料、サブスクリプション(動画・音楽配信など)の月額料、奨学金の返済、定期券代など。 - 変動費 (Hendo-hi):
月によって支出額が変動するもの。主に自分の日々の行動や選択によって、コントロール(節約)しやすい支出です。
(例) 食費、日用品費、交際費、趣味・娯楽費、交通費(定期券以外)、医療費、美容費など。
なぜこの分類が有効なのでしょうか?
それは、家計を見直す(節約する)際の優先順位が明確になるからです。
家計を本気で改善したい場合、まずメスを入れるべきは「固定費」です。「変動費」の食費を毎日100円切り詰める努力よりも、「固定費」のスマートフォン料金プランを一度見直して月2,000円安くするほうが、効果は絶大です。一度見直せば、その節約効果が自動的にずっと続くからです。
まずは「自分は毎月、自動的にいくら支払っているのか(固定費)」を把握することが、家計管理のスタートラインです。
方法2:支出を「大項目」10個程度から始める
固定費・変動費の分類と並行して、具体的な支出を記録するために、まずは「大項目」を10個程度に絞って設定しましょう。
家計簿アプリなどでは最初から多くの費目が設定されていることもありますが、多すぎると混乱します。最初は「食費」「交通費」といった大きな括り(大項目)だけを設定し、慣れてきたら「中項目(例:食費の中の外食費)」を追加する、というステップアップがおすすめです。
【初心者向け大項目10個の分類例(一人暮らし社会人)】
- 住居費 (固定費): 家賃、管理費、駐車場代など
- 水道光熱費 (固定費/変動費): 電気、ガス、水道代
- 通信費 (固定費): スマートフォン代、インターネット代
- 保険・その他固定 (固定費): 生命保険料、奨学金返済、サブスク代など
- 食費 (変動費): 食材、外食、カフェ、飲み会代もすべて含む
- 日用品費 (変動費): 洗剤、ティッシュ、掃除用品など
- 趣味・娯楽 (変動費): 書籍、映画、旅行、習い事など
- 交際費 (変動費): プレゼント代、友人との(食費以外の)付き合い
- 医療・美容 (変動費): 病院代、薬代、美容院、化粧品
- その他(雑費・予備費) (変動費): 上記に当てはまらないもの、分類に迷うもの
(ポイント)
- ライフスタイルに合わせて調整: 実家暮らしなら「住居費」「水道光熱費」はなく、「実家に入れるお金」という項目になるかもしれません。
- 「食費」と「交際費」: 飲み会代を「食費」に入れるか「交際費」に入れるか悩むところですが、「友人との食事はすべて交際費」のようにマイルールを決めてしまえばOKです。最初は「食費」に全部まとめてしまうのが一番簡単です。

「ざっくり管理」とは、手を抜くことではありません。継続するために、あえて管理のハードルを下げるという賢い選択です。まずは「固定費」と「変動費」の視点を持ちましょう。
これはどこ?分類に迷う支出の現実的な扱い方
家計簿を実際につけ始めると、必ず「これは、どの費目に入れればいいの?」と迷う支出が出てきます。
家計簿の「あるある」な悩みであり、多くの人がここで思考停止して挫折してしまいます。
【分類に迷う代表例】
- 例1:コンビニでパン(150円)と洗剤(300円)を一緒に買った。(クイズ内容より)
- 例2:ドラッグストアで薬(医療費)とトイレットペーパー(日用品)を買った。
- 例3:友人とのランチ代(交際費?食費?)
ここで「すべての支出を完璧に分類すべきだ」という完璧主義が顔を出すと、「レシートを見て1円単位で『食費 150円』『日用品 300円』と厳密に分けなければ…」となりがちです。しかし、これを毎回やるのは非常に手間がかかります。
継続しやすくするための現実的な対処法は、「自分なりの簡単なマイルール(割り切り)を決めておく」ことです。ルールを厳格にしすぎないことが、何より大切です。
割り切った「マイルール」の具体例
- 金額が最も大きい(メインの)費目に含める (推奨)
先の例1(パン150円、洗剤300円)であれば、金額の大きい「日用品」(300円)のほうに、合計金額450円をすべて計上してしまう方法です。
「洗剤を買いに行ったついでにパンを買った」と考えれば、主な目的は「日用品」です。これならレシートを分ける手間がありません。1ヶ月トータルで見れば、数百円のズレは家計全体(支出の傾向)に大きな影響を与えません。 - 「雑費」として記録する (注意が必要)
分類が面倒なものを、いったん「雑費」に入れてしまう方法です。これは簡単ですが、「雑費」が多発すると、後で解説するように「何に使ったか分からないお金」が増える原因になるため、多用は禁物です。 - 「コンビニ代」「ドラッグストア代」という費目を新設する (非推奨)
「コンビニでの買い物をすべてまとめる」という費目を作ってしまう人もいますが、これはお勧めできません。なぜなら、「コンビニ代 10,000円」という集計結果が出ても、その中で「食費」にいくら使ったのか、「日用品」や「雑誌(趣味)」にいくら使ったのかが全く分からなくなるからです。これでは分析ができず、家計簿の意味が薄れます。
家計簿の継続の鍵は、「1円単位の正確さ」よりも、「記録を止めないスピード感」です。「迷ったら、一番金額が大きい費目に入れる」といったマイルールを一つ決めておくだけで、日々の記録が格段に楽になります。

1円単位の正確さにこだわるあまり、記録に10分悩むのは時間の無駄です。「迷ったらメインの費目に計上する」というマイルールで、10秒で記録を終わらせましょう。
「雑費」が多すぎる?費目分けのゴールと見直し方
家計簿の費目として「雑費(または『その他』)」は、分類に迷う支出を一時的に受け止めてくれる、便利な項目です。
「『雑費』という項目は作ってはいけない」と厳しく考える必要はありません。むしろ、少額で分類に困る支出のために、雑費の枠はあったほうが現実的です。
しかし、この「雑費」に頼りすぎると、家計管理における非常に大きな落とし穴にはまります。
月末に集計した際、「雑費」の項目が異常に多くなってしまう(例えば、支出全体の20%以上を占めている)場合、その原因として最も考えられるのは、「分類ルールが曖”であり、何でもかんでも雑費に入れてしまっている」ことです。
なぜ「雑費」が多いとダメなのか?
家計簿の円グラフを見たときに、「食費 30%、趣味 10%、交際費 10%、そして雑費 50%」となっていたらどうでしょうか。
支出の半分が「何に使ったか分からないお金(=ブラックボックス)」であることを意味します。これでは、いくら家計簿をつけても「支出傾向の把握」も「改善」もできません。「雑費」は、家計簿の目的そのものを無意味にしてしまう可能性があるのです。
「雑費」との賢い付き合い方
もし「雑費」が多くなってしまったら、それは家計簿をやめる理由ではなく、「費目分けを見直すチャンス」だと捉えましょう。
- 「雑費」の中身を分析する
月末に一度、「雑費」として計上したレシートや履歴を振り返ってみてください。その中身をよく見ると、「これは、本当は『日用品』だったな」「これは『交際費』だ」と、既存の費目に振り分けられるものが多くあるはずです。 - 頻出する支出は「新費目」に独立させる
雑費の中身を分析した結果、例えば「ペット関連の支出」や「子供関連の支出」が毎月一定額発生していることがわかったら、それはもう「雑費」ではありません。「ペット費」「こども費」として新しい費目に独立させましょう。 - 「雑費」にも予算枠を設ける
「雑費は月5,000円まで」のように、あらかじめ予算枠を決めておくのも有効な管理方法です。
「雑費」は「未分類ボックス」だと考え、月末にこのボックスを開けて中身を整理整頓する習慣をつけることが重要です。
費目分けの真のゴール
ここまで費目分けの方法について解説してきましたが、忘れてはならないのは、費目分けの「ゴール」です。
費目分けの正解は、一つではありません。SNSで見た理想の分類でも、雑誌に載っている標準的な分類でもありません。
費目分けの真のゴールは、「自分の支出傾向を知り、改善すること」です。そして、そのために最も重要なのが「継続できること」です。
初めて家計簿をつける人が最も優先すべきことは、1円単位で正確に分類すること(完璧主義)ではなく、継続できる「ざっくり管理」の仕組みを自分なりに作ることなのです。
自分に合わない細かいルールや、他人の基準を真似ても長続きしません。自分にとって管理しやすく、ストレスなく継続できる分類方法こそが、あなたにとっての唯一の「正解」です。
そして、ライフスタイル(就職、引越し、結婚、転職など)が変われば、お金の使い方も変わります。その時は、費目も柔軟に「見直し(メンテナンス)」していきましょう。家計簿は、あなたの人生と共に成長させていくものなのです。

「雑費」は家計のブラックボックスです。月末にこのボックスを開けて中身を確認する作業こそが、家計改善の宝探しになります。雑費ゼロを目指すのではなく、雑費を管理下に置くことを目指しましょう。
まとめと最初のアクション
今回は、家計簿を継続するための「費目分け」のコツについて、挫折する原因から具体的な管理方法まで詳しく解説しました。
- 費目とは、支出を分類するカテゴリ(食費、交通費など)のことで、家計簿の「集計」「反省」の土台となります。
- 挫折の主な原因は、「完璧主義(細かく分けすぎる、1円単位にこだわる)」や「他人との比較」です。
- 継続のコツは、「ざっくり管理」です。まずは「固定費」と「変動費」に大別することから始めましょう。
- 分類に迷う支出は、「金額が最も大きい費目に入れる」など、自分なりの「マイルール」を決めて、悩む時間をなくしましょう。
- 「雑費」は便利ですが、多用は禁物です。月末に中身を分析し、費目分けを見直すきっかけにしましょう。
- 真のゴールは、完璧な分類ではなく、継続して支出傾向を把握・改善することです。
家計簿は、あなたを縛り付けるためのものではなく、あなたがお金を上手にコントロールし、未来の選択肢を増やすための強力なツールです。
難しく考えず、まずは「自分のお金の流れを知るゲーム」だと思って、気軽な第一歩を踏み出してみませんか?
【最初のアクション提案】
いきなり明日から完璧な記録を目指す必要はありません。
まずは、あなたの支出を「固定費」と「変動費」の2つに分ける作業から始めてみましょう。
紙とペンを用意して、
- 固定費(毎月ほぼ固定額で出ていくもの)
(例:家賃、スマホ代、ネット代、サブスク代、奨学金返済…) - 変動費(月によって変動するもの)
(例:食費、日用品費、交際費、趣味代、交通費…)
それぞれ何があるか、思いつくだけ書き出してみてください。
もし先月のクレジットカードの明細や銀行の履歴があれば、それを見るとより正確に把握できます。
自分が毎月、意識しなくても「自動的に」いくら支払っているのか(固定費)を知ること。それが、家F計管理の最も重要なスタートラインです。

まずは「固定費」と「変動費」を書き出すことから。自分が毎月いくら「自動的に」支払っているかを知ることが、家計改善のスタートラインです。最初の一歩を踏み出してみましょう。
このページの内容の理解度をクイズでチェック!
免責事項
本記事は、一般的な企業・業界情報および公開資料等に基づく執筆者個人の見解をまとめたものであり、特定の銘柄や金融商品への投資を推奨・勧誘するものではありません。また、記事内で取り上げた見解・数値・将来予測は、執筆時点の情報に基づくものであり、その正確性・完全性を保証するものではありません。今後の市場環境や企業動向の変化により、内容が変更される可能性があります。
本記事に基づく投資判断は、読者ご自身の責任と判断において行ってください。 本記事の内容に起因して生じたいかなる損失・損害についても、当サイトおよび執筆者は一切の責任を負いません。本記事は金融商品取引法第37条に定める「投資助言」等には該当せず、登録金融商品取引業者による助言サービスではありません。