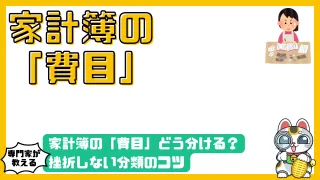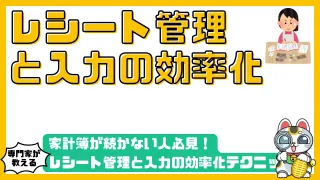本ページはプロモーションが含まれています。
このページの内容の理解度をクイズでチェック!
目次
はじめに
「今年こそ家計簿をつけるぞ!」
新しい年や新年度、新生活のスタートに合わせて、多くの人がそう決意します。家計簿は、自分のお金の流れを把握し、無駄遣いを減らし、将来のための貯蓄や投資に回すお金を生み出すための、家計管理における最強のツールの一つです。
しかし、その一方で、「家計簿を始めたはいいが、数週間、あるいはたった数日で記録が止まってしまった」という「三日坊主」の経験を持つ人も、同じくらい多いのではないでしょうか。
なぜ、家計簿の継続はこれほどまでに難しいのでしょう?
この記事は、まさにそんな「家計簿を続けたいのに、なぜか続かない」と悩む、高校生や新社会人の皆さんに向けて書いています。家計簿が続かないのは、決してあなたの意志が弱いから、あるいはズボラだからではありません。そのほとんどは、家計簿の「始め方」や「捉え方」に、挫折しやすい「罠」が潜んでいるからです。
この記事では、まず家計簿が続かない根本的な原因を徹底的に解剖します。そして、その原因を取り除き、無理なく、場合によっては楽しみながら家計簿を継続するための具体的なコツを、これでもかというほど詳しく解説します。
この記事を最後まで読めば、あなたは「完璧な記録」という重いプレッシャーから解放され、「継続すること」で着実に家計を改善していく、本当の家計管理の第一歩を踏み出せるはずです。

家計管理の第一歩は、自分のお金の流れを知ることから始まります。しかし、そのための家計簿で挫折していては本末転倒です。まずは「続ける」ための技術を学びましょう。
なぜ家計簿は「三日坊主」で終わるのか?その原因を徹底解剖
家計簿が続かないのには、いくつかの非常に明確で、多くの人に共通する理由が存在します。まずは「敵」を知ることから始めましょう。あなたが過去に挫折した理由も、この中にきっとあるはずです。
最大の原因は「完璧主義」という名の呪縛
家計簿挫折の最大の原因、それは「完璧主義」です。
新しく家計簿を始めるとき、私たちはつい意気込みすぎてしまいます。「すべての支出を1円単位で正確に記録しよう」「食費、日用品、交通費…と細かく項目を分けて、完璧に管理しよう」「毎日、寝る前に必ず記録する時間を取ろう」——。
この「完璧にやろう」という意気込みこそが、継続を妨げる最大の障害となります。
最初は高いモチベーションで続けられても、一度でも記録を忘れたり、月末に計算が合わなかったり(「使途不明金」が発生したり)すると、「ああ、もうダメだ」「完璧にできなかった」と、一気にやる気が失せてしまいます。そして、その一度の失敗がきっかけで、記録すること自体をやめてしまうのです。
高すぎる「初期ハードル」の設定
完璧主義とも関連しますが、最初から「高すぎるハードル」を設定してしまうことも、挫折の大きな原因です。
- 手間がかかりすぎる: 手書きのノートに、レシートを見ながら日付、店名、品目、金額をすべて書き写す。あるいは、家計簿アプリで細かくカテゴリ分類し、メモまで入力する。こうした「記録の手間」が面倒になり、だんだん億劫になっていきます。
- いきなり高目標を立てる: 家計簿をつけるのと同時に、「今月から食費を2万円に抑える!」といった高い節約目標を立ててしまうケースです。記録するだけでも大変なのに、さらに節約のプレッシャーも加わり、二重の苦しさで続かなくなります。
- 高機能アプリを使いこなそうとする: グラフ機能、予算管理、資産連携など、機能が豊富なアプリは魅力的です。しかし、最初からすべての機能を使いこなそうとすると、設定や操作を覚えるだけで疲弊してしまい、「面倒だからもういいや」となりがちです。
目的の曖昧さ:「何のために」が抜けている
三つ目の大きな原因は、そもそも「何のために家計簿をつけるのか」という目的が曖昧なまま始めてしまうことです。
家計簿をつけることは、あくまで「手段」です。その先にある「目的」、たとえば「毎月あと1万円多く貯金したい」「趣味の旅行に行く費用を貯めたい」「将来の一人暮らしに備えたい」といった具体的なゴールがなければ、面倒な作業を続ける意味を見失いがちです。
ただ記録するだけで満足してしまい、「記録したデータを見返して、次どうするか」という行動に移せないと、「家計簿をつけているのに何も変わらない」「時間を無駄にしている気がする」と感じ、やがて挫折してしまいます。家計簿をつけることが目的化してしまうと、継続は困難です。

多くの人が「記録すること」の完璧さを求めすぎて挫折します。原因が分かれば対策は簡単です。なぜ続かないのか、自分のケースに当てはめて考えてみましょう。
家計簿の挫折は「完璧主義」が原因?1円単位の記録は不要
家計簿挫折の最大の敵が「完璧主義」であることは分かりました。では、その「完璧主義」の呪縛から逃れるためには、具体的にどう考え、どう行動すればよいのでしょうか。
「1円でも合わないとダメ」という考えを捨てる
家計簿をつけていると、月末に「あれ、財布の中身と残高が100円合わない」「使途不明金が500円ある」といった事態が必ず発生します。
完璧主義の人は、ここで「合わない!気持ち悪い!原因を突き止めるまで寝られない!」と、レシートの束とにらめっこしたり、記憶を必死で辿ったりして、多大な時間とエネルギーを浪費してしまいます。そして、これに疲れて家計簿自体が嫌になります。
断言します。家計簿は、1円単位で合わせる必要はまったくありません。
家計簿の目的は、警察の捜査や企業の経理処理のように1円の誤差もなくすことではなく、自分のお金の流れの「大きな傾向」を把握することです。
たとえば、「今月は食費が5万円、交際費が3万円かかった」という事実が分かれば、「来月は食費を4万5千円に、交際費を2万5千円に抑えよう」という対策が立てられます。そこに数百円の誤差があったとしても、この「対策を立てる」という本質的な行動には何の影響もありません。
使途不明金は「雑費」や「不明金」として処理し、「まあ、こんなものか」と気にせず先に進む「ゆるさ」を持つこと。これが継続の第一の鍵です。
「毎日必ず記録」というルールは不要
「毎日寝る前に記録する」というルールも、非常に挫折しやすい典型的なパターンです。
仕事や学業で疲れて帰ってきた日、友人との予定で帰りが遅くなった日、体調が悪い日…。「毎日」というルールは、こうしたイレギュラーな日にいとも簡単に破綻します。
そして、一度破綻すると「昨日できなかったから、もういいや」と、そのままフェードアウトしてしまうのです。
これも、「ゆるさ」で解決できます。
- 記録できない日があっても気にしない: 記録できない日があっても、自分を責めないこと。「疲れているから明日にしよう」と割り切って寝てしまいましょう。
- 「記録日」を決める: 毎日ではなく、「3日に1回」や「週末の土曜日にまとめて」など、自分のペースで記録日を決めます。
- レシートを箱に入れるだけ: 毎日やることを「レシートを決まった箱に入れる」だけにします。記録は週末にまとめて行えばよいのです。これなら1日10秒で終わります。
大切なのは、完璧な記録ではなく、「途中で投げ出さずに続けること」を最優先する心構えです。1円の誤差や数日の記録漏れよりも、途中でやめてしまうことのほうが、家計管理においてはよっぽど大きな「損失」なのです。

100円合わない理由を探すために1時間悩むのは、時給1000円のアルバイトをしている人なら900円の「機会損失」です。その「ゆるさ」が継続の鍵であり、経済的合理性でもあります。
挫折しない第一歩:「ハードルを下げる」具体的な工夫
家計簿を継続する秘訣は、とにかく「ハードルを下げる」ことです。
スポーツや勉強と同じで、いきなりプロ選手と同じ練習をしようとしても続くわけがありません。自分が「これなら息切れせずに続けられそう」と思える、ごくごく簡単なレベルからスタートするべきです。
ここでは、家計簿のハードルを劇的に下げるための、具体的な3つの工夫を紹介します。
工夫1:記録の「頻度」を思い切り下げる
前章でも触れましたが、「毎日記録」という高いハードルは、挫折の王道です。この頻度を思い切り下げてみましょう。
- 「週に1回」ルール: 「毎週土曜日の夜、お風呂に入る前に10分だけ」など、生活のルーティンの中に組み込んでしまいます。1週間分のレシートをまとめて入力するだけなら、それほど大きな負担にはなりません。
- 「月に1回」ルール(上級者向け): これは、ある程度キャッシュレス決済が進んでいる人向けですが、クレジットカードの明細や銀行口座の履歴(通帳やネットバンキング)を月に一度だけチェックし、大きな支出の傾向だけを把握する方法です。日々の細かい支出は追いませんが、家計全体の大きな動きは掴めます。
まずは「週1回」から始め、もしそれが楽しくなってきたら「3日に1回」にしてみるなど、徐々に自分の最適なペースを探っていけばよいのです。
工夫2:記録する「項目」を限界まで絞り込む
家計簿アプリやノートを開くと、「食費」「日用品」「交通費」「交際費」「趣味・娯楽費」「水道光熱費」「通信費」「家賃」…と、無数のカテゴリ(費目)が並んでいます。
これをすべて正確に分類しようとすると、すぐに面倒になります。「このコンビニで買ったお茶は『食費』? それとも『日用品』?」などと悩む時間が発生し、これがストレスになります。
最初は、項目を限界まで絞り込みましょう。
- 究極の3分類: たとえば、「①固定費(家賃、スマホ代など)」「②変動費(食費、交際費など)」「③貯金」の3つだけ記録する。
- 「変動費」だけ記録する: 家賃やスマホ代、光熱費など、毎月だいたい決まって出ていく「固定費」は、一度把握したら記録対象から外してしまいます。記録するのは、月によって変動し、かつ自分でコントロールしやすい「変動費」(食費、交際費、趣味費など)だけに絞ります。これだけでも、記録の手間は半分以下になります。
まずは大きな支出項目だけ記録し、慣れてきたら「食費の内訳(自炊、外食)」など、自分が気になるところだけ細分化していけばOKです。
工夫3:「ツール」を徹底的に活用し、入力を自動化する
現代の家計管理において、テクノロジーを使わない手はありません。手書きには手書きの良さ(お金を使った実感が湧く、記憶に残りやすい)がありますが、継続のハードルを下げる上では、ツールの活用が最も効果的です。
- 家計簿アプリの「自動連携」: これが最強の時短テクニックです。多くの家計簿アプリには、銀行口座やクレジットカード、電子マネー(Suica, PayPayなど)と連携する機能があります。一度設定してしまえば、あなたがキャッシュレスで支払った履歴は、日付、金額、店名が自動で家計簿に記録されます。あなたがやることは、たまにアプリを開いて、自動分類されたカテゴリが合っているか確認するだけです。
- レシート撮影(OCR)機能: 現金で支払った場合も、レシートをスマートフォンのカメラで撮影するだけで、内容を自動で読み取ってくれる機能があります。手入力する手間が大幅に削減されます。
もちろん、「高機能なアプリを導入したから続く」わけではありません。アプリの機能に振り回されず、「自動連携」や「レシート撮影」といった、自分の手間を減らしてくれる機能を賢く利用することがポイントです。

新しい習慣を身につけるには「ベイビーステップ」が鉄則です。レシートを撮影するだけ、週に一度だけ。まずは「ゼロ」を「イチ」にすることだけを考えましょう。
家計簿は「つけること」が目的ではない?目的の明確化と振り返り
ハードルを下げ、記録が続けられるようになってきたら、次のステップに進みましょう。それは、家計簿をつける「本来の目的」を思い出し、行動に移すことです。
もし家計簿を「つけること」自体が目的になってしまうと、それは単なる「作業」になってしまい、やがて「何のためにこんな面倒なことを…」と虚しくなり、挫折に繋がります。
なぜ、あなたは家計簿をつけるのか?
家計簿は、あなたの「夢」や「目標」を叶えるための「手段」です。家計簿をつけることで、家計の無駄(ブラックボックス)を見つけ、その無駄を「貯蓄」や「自己投資」に振り分ける原資を生み出すのです。
あなたが家計簿をつける目的は、何でしょうか?
- 高校生なら: 「欲しいゲームソフトを買うため」「友達との旅行費用を貯めるため」「お小遣いやアルバイト代の範囲で上手にやりくりするため」
- 大学生・専門学生なら: 「サークルや交際費を捻出するため」「留学や資格取得の費用を貯めるため」「奨学金の繰り上げ返済に備えるため」
- 新社会人なら: 「初めての一人暮らしの生活費を安定させるため」「毎月5万円を貯金に回すため」「将来のための投資(NISAなど)の種銭を作るため」
このように、具体的でワクワクするような目的を明確に持つことが、面倒な記録作業を続けるための強力なモチベーション(動機付け)になります。
「記録するだけ」で満足してはいけない
「家計簿をつけるだけでお金が貯まる」——これは、残念ながらよくある誤解です。「体重計に毎日乗るだけでダイエットに成功する」というのが誤解であるのと同じです。
家計簿(データ)は、体重計(数値)と同じ。重要なのは、そのデータを見て「次どうするか」を考え、行動することです。これが「振り返り」です。
- 「記録」と「振り返り」はセット: 記録が1週間分、あるいは1ヶ月分たまったら、必ずそのデータを見返しましょう。
- 「振り返り」でやること:
- 傾向の把握: 「今月は外食が多かったな」「思ったより趣味にお金を使っているな」と、自分のお金の使い方(消費行動)の客観的な傾向を把握します。
- 原因の分析(反省ではない): 「なぜ外食が多かった?」「仕事が忙しくて自炊できなかったからだ」と、原因を分析します。この時、「使いすぎた!」と自分を責める必要はありません。事実を淡々と確認します。
- 改善アクションの決定: 「じゃあ来月は、週に2回は簡単な自炊(冷凍食品やレトルトでもOK)をしよう」「忙しい日のために、安いお弁当屋を見つけておこう」と、次につながる具体的な行動(改善アクション)を決めます。
小さな成果(スモールウィン)を可視化する
この「記録 → 振り返り → 改善」というサイクル(PDCAサイクルとも呼ばれます)を回し始めたら、ぜひ「小さな成果」に注目してください。
「先月より食費が2,000円減った!」
「今月は予算内で生活できた!」
「無駄なサブスク(定額課金サービス)を1つ解約できた!」
こうした「小さな成功体験(スモールウィン)」を可視化し、自分で自分を褒めることが、次の月も頑張ろうという継続のエネルギーになります。家計簿アプリのグラフで支出が減っているのを確認するのも良いでしょう。
家計簿の本来の目的は、この「改善サイクル」を回し、自分の家計をより良くコントロールしていくことにあるのです。

記録は「過去」のデータですが、振り返りは「未来」の行動を変えるためにあります。データを見て「次どうするか」を考えることこそが、家計簿の本当の価値です。
完璧な記録より「継続」が家計改善への最短ルート
ここまで、家計簿が続かない原因と、それを克服するための具体的な方法(ハードルを下げる工夫、目的の明確化)について、詳しく解説してきました。
最後に、家計簿と向き合う上で最も重要なたった一つの「心構え」についてお話しします。
「完璧な1ヶ月」より「大雑把な1年間」
もし、あなたが家計簿で本当に家計を改善したいと願うなら、絶対に忘れないでほしいことがあります。
それは、家計簿で最も大切なのは「完璧な記録」ではなく、「とにかく継続すること」だということです。
1円単位で完璧に記録された、たった1ヶ月分のデータ。
それと、多少の誤差や記録漏れはあっても、大雑把に1年間続いたデータ。
家計改善において、どちらが価値があるか。答えは明白です。圧倒的に後者(1年間のデータ)です。
なぜなら、たった1ヶ月のデータでは、それが「たまたま」なのか「いつも通り」なのか判断できないからです。しかし、1年間データが蓄積されれば、あなたの家計の「本質」が見えてきます。
- 「夏は光熱費(冷房代)が上がるが、冬はもっと上がる(暖房代)」
- 「年末年始とゴールデンウィークは、交際費と交通費が跳ね上がる」
- 「ボーナス月は気が大きくなって、謎の支出が増えている」
こうした「自分のお金の使い方のクセ」や「季節変動」が明確にわかってこそ、的確な年間予算を立てたり、長期的な貯蓄計画を実行したりすることが可能になるのです。
家計簿は、あなたの家計の「健康診断」のようなものです。半年に一度、あるいは年に一度の健康診断が重要なように、家計簿も継続してこそ、あなたの家計の「健康状態」を正確に示してくれるのです。
合わなければ、すぐに「やめる」勇気
継続が大切だ、と繰り返してきましたが、それは「一つの方法を我慢して続けろ」という意味ではありません。
「手書きノートで始めたけど、やっぱり面倒だ」
「このアプリ、高機能だけど自分には合わない」
そう感じたら、すぐにその方法をやめて、別の方法を試してください。
家計簿の「方法(手段)」にこだわる必要は一切ありません。Aさんにとって最高の方法が、あなたにとっても最高であるとは限りません。
手書き、アプリ、Excel、レシートを箱に入れるだけ…世の中には無数の家計簿術があります。大切なのは、あなたが「これなら無理なく続けられそうだ」と感じる、自分に合った「ゆるい」方法を見つけるまで、試行錯誤を恐れないことです。
家行簿は、あなたを縛り付けるための「枷(かせ)」ではありません。あなたを経済的な自由へと導くための「羅針盤」です。完璧さを捨て、ハードルを下げ、自分に合った羅針盤を手に入れ、無理なく「継続」という航海を楽しみましょう。

家計簿は、短距離走ではなくマラソンです。完璧なフォーム(記録)より、完走(継続)することが、目的地(家計改善)にたどり着く唯一の方法です。
まとめとやるべきアクション
今回は、「挫折しない家計簿の続け方」について、その原因から具体的な対策、そして最も重要な心構えまでを網羅的に解説しました。
家計簿の挫折は、あなたの意志の弱さが原因ではありません。その多くは、スタート地点での「完璧主義」や「高すぎるハードル」設定に問題があります。
家計簿を無理なく続けるための鍵は、以下の4つに集約されます。
- 完璧主義を捨てる: 1円の誤差や、記録できない日があっても気にしない「ゆるさ」を持つこと。家計簿は「傾向」がわかれば十分です。
- ハードルを極限まで下げる: 「週1回だけ」「大きな項目だけ」「アプリで自動連携するだけ」など、自分が息切れせずにできる最低限のレベルから始めること。
- 目的を明確にする: 「つけること」を目的とせず、「貯蓄」「旅行」「投資」など、その先にあるポジティブな目標を意識し、「記録→振り返り→改善」のサイクルを回すこと。
- 「継続」を最優先する: 完璧な記録よりも、「大雑把でもいいから続けること」を最重要のミッションとすること。継続したデータこそが、あなたの家計を改善する最大の資産となります。
家計簿は、あなたのお金の使い方を客観的に映し出す「鏡」です。鏡がなければ、自分の姿を正すことはできません。
この記事を読んで「続けるコツ」がわかったら、次は行動に移す番です。「知っている」ことと「できる」ことの間には、大きな壁があります。その壁を越えるのは、ほんの「小さな一歩」です。
さあ、今すぐ、あなたにとって最もハードルが低いと思う「家計簿の第一歩」を踏み出してみましょう。
いきなりアプリをダウンロードしたり、ノートを買ったりする必要さえありません。
まずは今週1週間、自分が最も「ハードルが低い」と感じる方法を1つだけ決めて実行してみましょう。
- 「財布から出たレシートを、全部決まった箱に入れる(記録はしない)」
- 「週に一度だけ(例えば土曜日に)、銀行口座のネットバンキングにログインして残高を眺める」
- 「今週使った一番大きな買い物の金額だけ、スマホのメモ帳に書き出す」
そんな、誰にでもできる小さな一歩が、あなたの家計と未来を大きく変える、確実なきっかけになるはずです。

「知る」と「やる」の間には大きな壁があります。この記事で「続けるコツ」を知った今、大切なのは「小さな一歩」を踏み出すことです。今週から、始めてみませんか。
このページの内容の理解度をクイズでチェック!
免責事項
本記事は、一般的な企業・業界情報および公開資料等に基づく執筆者個人の見解をまとめたものであり、特定の銘柄や金融商品への投資を推奨・勧誘するものではありません。また、記事内で取り上げた見解・数値・将来予測は、執筆時点の情報に基づくものであり、その正確性・完全性を保証するものではありません。今後の市場環境や企業動向の変化により、内容が変更される可能性があります。
本記事に基づく投資判断は、読者ご自身の責任と判断において行ってください。 本記事の内容に起因して生じたいかなる損失・損害についても、当サイトおよび執筆者は一切の責任を負いません。本記事は金融商品取引法第37条に定める「投資助言」等には該当せず、登録金融商品取引業者による助言サービスではありません。