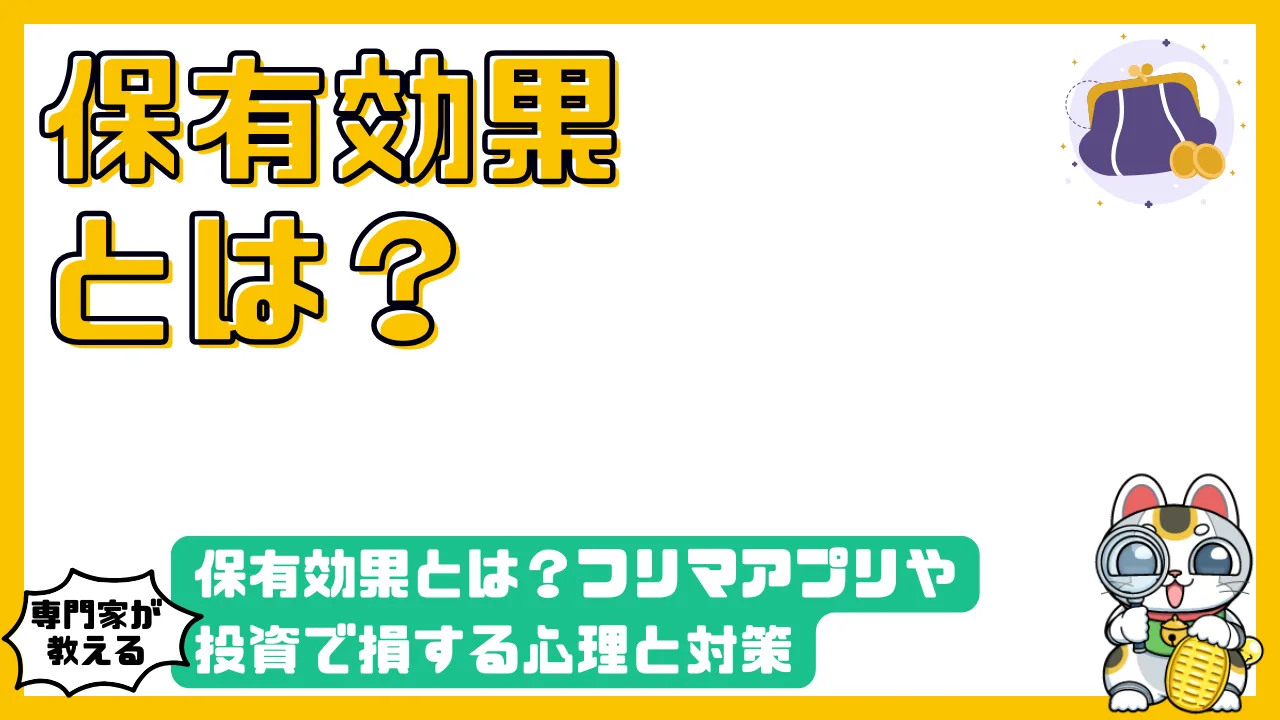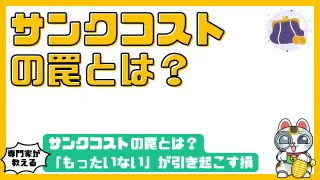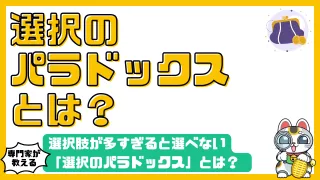本ページはプロモーションが含まれています。
このページの内容の理解度をクイズでチェック!
目次
はじめに
「大切にしてきたコレクションをフリマアプリに出品しようとしたら、どうしても相場より高い値段を付けたくなってしまう」
「無料お試し期間が終わったサブスクリプション(月額課金サービス)を、あまり使っていないのに解約しそびれている」
「値下がりしてしまった株式や投資信託を、『いつか戻るはず』と信じて、売る決心がつかない」
こうした経験は、誰にでもあるのではないでしょうか。
大切なお金や資産に関わる判断であるにもかかわらず、なぜか合理的に行動できない。その背景には、人間の「心のクセ」、つまり認知バイアスが隠れています。
この記事では、そうした心のクセの中でも特に強力で、私たちの経済活動に大きな影響を与える「保有効果(ほゆうこうか)」について、行動経済学の視点からわかりやすく解説します。
行動経済学とは、従来の経済学が「人間は常に合理的に判断する」と仮定していたのに対し、「人間は感情的で、時には不合理な判断もする」という現実の姿に着目し、その心理的なメカニズムを解き明かす学問です。
この記事を最後まで読めば、あなたが「なぜ自分の持ち物を高く評価してしまうのか」を理解できるだけでなく、その心理がフリマアプリでの値付けや、大切な資産運用(投資)においてどのような「落とし穴」となるのか、そしてその落とし穴を避けるための具体的な対策まで、深く学ぶことができます。

行動経済学は、私たちがついやってしまう「不合理な行動」の理由を教えてくれます。まずは「自分もそうかもしれない」と、自分の心のクセを知ることから始めましょう。
保有効果とは?「持っている」だけで価値が上がる心理
保有効果(ほゆうこうか)とは、自分が一度所有したものに対し、それを持っていない時よりも高い価値を感じ、手放すことに強い抵抗を感じるという心理現象を指します。「授かり効果」や「エンダウメント効果(Endowment Effect)」とも呼ばれます。
この現象を有名にしたのが、行動経済学者たちが行った「マグカップの実験」です。
被験者をAとBの2つのグループに分け、Aグループには大学のロゴ入りマグカップを無料で配布し、Bグループには何も配りませんでした。その後、以下の質問をします。
- Aグループ(売る側): 「そのマグカップをいくらからなら売りますか?」
- Bグループ(買う側): 「そのマグカップをいくらまでなら買いますか?」
もし人間が合理的にそのマグカップの「客観的な価値」を判断できるなら、Aグループが提示する「売値」とBグループが提示する「買値」は、ほぼ同じになるはずです。
しかし、実験結果は大きく異なりました。例えば、Aグループ(売る側)が「700円」の値段を付けたのに対し、Bグループ(買う側)は「350円」までしか払う気がない、といったように、売る側の希望価格が、買う側の希望価格の約2倍にもなったのです。
マグカップの客観的な価値は何も変わっていません。変わったのは、「自分のものになった」という事実だけです。一度「自分のもの」と認識した途
端、その価値が自分の中で(客観的な価値以上に)釣り上がってしまう。これが保有効果の正体です。
ほかの似たような心理との違い
この保有効果は、お金の判断を鈍らせる他の心理バイアスと混同されがちですが、明確な違いがあります。
- サンクコスト効果(埋没費用):
「これまでに費やした時間やお金がもったいない」と感じ、損失が出ているとわかっていても継続してしまう心理です。(例:つまらない映画でも「チケット代がもったいない」と最後まで見てしまう) - 現状維持バイアス:
変化すること(何か新しく得る、あるいは失う)よりも、今の状態を維持することを無意識に好む心理です。(例:もっと良いプランがあっても「手続きが面倒」と携帯会社を乗り換えない)
保有効果は「自分の持ち物」を過大評価する心理です。
一方で、サンクコストは「過去に支払ったコスト」を惜しむ心理、現状維持バイアスは「変化そのもの」を避ける心理、という点で異なります。
ただし、これらのバイアスは互いに影響しあっており、例えば「値下がりした株を売れない」という行動には、保有効果とサンクコスト効果、現状維持バイアスのすべてが絡み合っていることも少なくありません。

マグカップの実験は、私たちがいかに「客観的な価値」ではなく「自分が所有しているか」でモノの値段を変えてしまうかを示しています。これは良い・悪いではなく、人間の基本的な性質なのです。
保有効果が起こるメカニズムと「損失回避」
では、なぜ私たちは、ただ「持っている」というだけで、そのモノの価値を高く評価してしまうのでしょうか。
その最も強力な理由として、行動経済学の「損失回避(そんしつかいひ)」という性質が挙げられます。これは、保有効果の根底にある、非常に重要な人間の心理特性です。
損失回避とは、ノーベル経済学賞を受賞した心理学者ダニエル・カーネマン氏らが提唱した「プロスペクト理論」の中核となる概念です。
これは、人は「何かを得る喜び」よりも、「同じ価値のものを失う苦痛」を約2倍から2.5倍も強く感じるという心理特性を指します。
簡単に言えば、「1万円を拾う喜び」よりも、「1万円を失う苦痛」のほうが、私たちの心に与えるインパクトが圧倒的に大きい、ということです。
この「損失回避」の性質が、保有効果と強く結びつきます。
マグカップの例に戻ると、
- 買う側(Bグループ)にとって、マグカップを手に入れることは「350円を失い、マグカップを得る」という「獲得(プラス)」の行為です。
- 売る側(Aグループ)にとって、一度「自分のもの」になったマグカップを手放すことは、「700円を得る」という喜びよりも、「マグカップを失う(マイナス)」という行為として認識されます。
一度自分のものになると、それを手放すことが「損失」として認識されるため、その「失う痛み」(1万円失う苦痛)を乗り越えるほどの、よほど大きな対価(2万円もらえる喜び)がなければ、手放す決断ができないのです。
そのため、失う痛みを補填するために、客観的な価値(350円)に「失いたくない」という感情的な価値が上乗せされ、結果として「700円」という高い売値を付けてしまう。これが保有効果が起こる中心的なメカニズムです。
もちろん、単純に自分の持ち物への「愛着」や、「自分の持ち物」=「自分自身の一部」であるという自己イメージが価値を上乗せしている側面もありますが、この「損失回避」の非対称な心理が、保有効果を生み出す根本的な原因と考えられています。

「1万円もらう嬉しさ」より「1万円失う苦しさ」の方が、心に強く響く。この「損失回避」の感覚こそが、保有効果のエンジンです。手放すことを「損失」と捉える心が、価格を釣り上げてしまうのです。
日常生活に潜む保有効果の落とし穴
保有効果は、実験室の中だけの特殊な話ではありません。私たちの日常生活の、お金が関わるあらゆる場面に潜んでおり、合理的な判断を妨げる「落とし穴」となっています。
1. フリマアプリでの高すぎる価格設定
最もわかりやすい例が、フリマアプリでの出品です。
自分が長年愛用した服、集めてきた趣味のコレクション、読み終えた本などを出品する際、「これくらいで売れるはず」と、市場の相場(実際に売れている価格)よりも明らかに高い値段を付けてしまうことはないでしょうか。
これは、その商品に対する「思い出」や「愛着」が価値に上乗せされていることに加え、「自分のもの」を手放す「損失の痛み」を避けたいという保有効果が強く働いている典型例です。
買い手は、その商品の客観的な価値(状態や希少性)しか見ていません。しかし、売り手は「自分にとってはこれだけの価値がある」という主観的な評価を優先してしまうため、いつまでも売れ残ってしまうのです。
2. 無料体験後のサブスクリプション継続
動画配信サービス、音楽アプリ、ビジネスツールなどでよく見かける「30日間無料お試し」や「初月無料」といったキャンペーンも、保有効果(と損失回避)を巧みに利用した仕組みです。
無料期間中、私たちはそのサービスを「自分のもの」として利用し、その利便性に慣れていきます。
そして無料期間が終了する時、サービスを「解約する」という行為は、一度手に入れた利便性や楽しみを「失う」ことを意味します。
この「失う痛み」を回避したいという心理が働き、「まあ、月額数百円だし、解約手続きも面倒だから」と、あまり利用していなくても有料プランへ自動移行し、そのまま継続してしまうケースは少なくありません。
3. 「いつか使うかも」と捨てられないモノ
「高かったから」「限定品だから」「いつか使うかもしれないから」という理由で、もう何年も使っていないモノがクローゼットや押入れを占領している状態も、保有効果が関係しています。
客観的に見れば、そのモノの現在の市場価値はゼロに近いかもしれません。
しかし、一度「自分のもの」として所有しているため、それを「捨てる(=所有権を手放す)」という決断ができません。「手放す=損失」と心が判断してしまうため、合理的な片付け(断捨離)の判断を妨げているのです。

「無料お試し」は、私たちに「所有感」を与えるための巧妙な仕掛けです。一度「自分のもの」として体験してしまうと、それを手放す(解約する)ことが「損失」に感じられ、やめられなくなるのです。
投資判断を鈍らせる保有効果の罠
こうした保有効果は、日常生活の小さな判断だけでなく、株式投資や投資信託(NISAやつみたてNISA、iDeCoなど)といった、将来の資産を左右する重要な「投資」の世界でも、深刻な落とし穴となります。
損切り(そんぎり)ができず「塩漬け」に
投資において保有効果が最も危険な形で現れるのが、「損切り(そんぎり)」の場面です。
損切りとは、購入した株式や投資信託が値下がりしてしまった場合に、将来のさらなる価格下落(損失拡大)を防ぐために、損失を確定させて売却することです。
もしその値下がりの理由が、一時的な市場の変動ではなく、その企業や市場の将来性が根本的に悪化したことによるものなら、合理的な判断は「これ以上損失が拡大する前に売却する(損切りする)」ことです。
しかし、保有効果が働くと、「自分が保有している銘柄」を過大評価してしまいます。
「これは自分が時間やお金をかけて分析して選んだ、良い銘柄のはずだ」
「きっとこれは一時的な下落で、いつか必ず価格は戻るはずだ」
このように、客観的なデータやニュースよりも、「自分の持ち株」であることをひいきしてしまい、売却のタイミングを逃してしまいます。
その結果、売るに売れず、大きな含み損を抱えたまま長期間保有し続ける、いわゆる「塩漬け(しおづけ)」の状態に陥ります。
これは、その資金が他の有望な投資先に回っていれば得られたはずの利益(機会損失)を失うだけでなく、さらに価格が下落して損失が拡大するリスクを抱え続けることになり、資産形成において非常に非合理的な行動と言えます。
保有効果は、冷静であるべき投資判断を「愛着」や「失う痛み」といった感情で鈍らせ、私たちを不合理な行動へと導く強力なバイアスなのです。

投資で最も難しいのは「損切り」です。保有効果は「まだ大丈夫」「いつか戻る」と囁きかけますが、その感情的な判断こそが、合理的な資産運用を妨げる最大の罠となります。
保有効果に振り回されないための3つの対策
では、この厄介な「保有効果」と、私たちはどう付き合っていけばよいのでしょうか。
保有効果は人間の本能的な心理であるため、完全になくすことは難しいと言われています。しかし、その存在を知り、対策を講じることで、その影響を最小限に和らげ、より合理的な判断をすることは可能です。
1. 「自分もバイアスにかかる」と自覚する
まず最も重要な第一歩は、「自分も保有効果の影響を必ず受ける」と自覚することです。「自分は合理的だから大丈夫」「自分は感情で判断しない」といった過信こそが、バイアスにはまる入り口になります。
「今、自分は保有効果にとらわれていないか?」と常に意識し、自分の判断を客観的に疑う癖をつけることが重要です。
2. 視点を変えて自問自答する
保有効果への対策として非常に強力で、すぐに実践できる思考法が、「もし今、自分これを持っていなかったとしたら、この価格でわざわざ買うだろうか?」と自問自答することです。
- フリマアプリの場合:
「もし自分が買い手だったら、この状態の中古品に、自分がいま付けようとしている金額を払うか?」 - 投資(塩漬け株)の場合:
「もし今、この株を持っておらず、同額の現金を持っていたとしたら、この銘柄を今日、新規で買うか?」
この問いの答えが「No」であるならば、あなたは保有効果によって、そのモノを過大評価している可能性が非常に高いです。
この質問は、あなたを「手放す痛み」に苦しむ所有者(売る側)の視点から、客観的な価値を判断する非所有者(買う側)の視点へと、強制的に切り替える(参照点をリセットする)効果があります。
この時、「いくらで買ったか」を基準に考えるのは禁物です。それは保有効果ではなく「サンクコスト効果」の罠であり、未来の価値判断には一切関係ありません。
3. 事前に「売るルール」を決めておく
特に感情が入り込みやすい投資判断においては、バイアスが入り込む余地を減らすことが重要です。
そのためには、金融商品を購入する前に、「売却のルール」を客観的な数字で明確に決めておくことが極めて有効です。
- 「購入価格から〇%値下がりしたら、理由を問わず機械的に損切りする」
- 「〇〇という客観的な経営指標が悪化したら、売却を検討する」
- 「フリマアプリでは、類似商品の『売却済み』の平均価格で出品する」
このように、感情(愛着や期待)ではなく、事前に決めた客観的なルールに基づいて行動することで、保有効果や損失回避といった感情的なバイアスに振り回されるリスクを格段に減らすことができます。

対策として最も強力なのは「もし今、これを持っていなかったら、この値段で買うか?」と自問することです。この「視点の転換」こそが、保有効果の呪縛から逃れるための鍵となります。
まとめと今日からできるアクション
今回は、私たちの合理的にお金の判断を鈍らせる強力な心のクセ、「保有効果」について詳しく解説しました。
- 保有効果とは、自分が所有するものを客観的な価値以上に高く評価し、手放すことに抵抗を感じる心理バイアスです。
- その背景には、人は「得る喜び」より「失う苦痛」を約2倍強く感じる「損失回避」の性質があります。
- 日常生活では、フリマアプリでの高値設定や、使わないモノを捨てられない原因となります。
- 投資の世界では、値下がりした株(塩漬け株)を過大評価し、損切りを妨げる原因となり、合理的な資産形成を阻害します。
この保有効果の恐ろしいところは、私たちが「意識しない限り」自動的に発動し、大切なお金に関する判断を歪めてしまうことです。
しかし、そのメカニズムを理解し、対策を知っていれば、その影響を最小限に抑えることができます。
- 対策1: まず「自分も保有効果にかかる」と自覚する。
- 対策2: 「もし今これを持っていなかったら、買うか?」と自問する。
- 対策3: 事前にルールを決め、感情ではなくルールに従う。
保有効果を理解することは、感情に流されず、合理的なお金の意思決定をするための第一歩です。
まずは、身近なところから始めてみましょう。
最近「手放すか迷っているもの」を1つ挙げてください。
それは、もう何年も着ていない服かもしれませんし、読み終えた本、あるいは含み損を抱えたままの金融商品かもしれません。
そして、自分にこう問いかけてみてください。
「もし今、これを持っていなかったら、わざわざお金を出してこれを買いますか?」
その答えが「いいえ」であるならば、あなたは保有効果の力に気づき、より賢明な判断を下すための一歩を踏み出せるはずです。

保有効果は、人間の自然な感情です。それを知った上で、「自問自答」という客観的な視点を持つツールを使いこなすことが、賢い金融生活を送るための知恵となります。ぜひ、今日から実践してみてください。
このページの内容の理解度をクイズでチェック!
免責事項
本記事は、一般的な企業・業界情報および公開資料等に基づく執筆者個人の見解をまとめたものであり、特定の銘柄や金融商品への投資を推奨・勧誘するものではありません。また、記事内で取り上げた見解・数値・将来予測は、執筆時点の情報に基づくものであり、その正確性・完全性を保証するものではありません。今後の市場環境や企業動向の変化により、内容が変更される可能性があります。
本記事に基づく投資判断は、読者ご自身の責任と判断において行ってください。 本記事の内容に起因して生じたいかなる損失・損害についても、当サイトおよび執筆者は一切の責任を負いません。本記事は金融商品取引法第37条に定める「投資助言」等には該当せず、登録金融商品取引業者による助言サービスではありません。