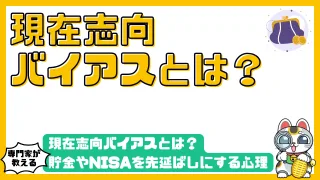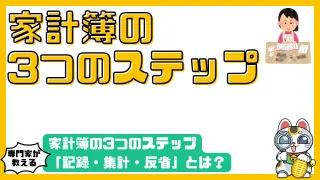本ページはプロモーションが含まれています。
このページの内容の理解度をクイズでチェック!
目次
はじめに
「毎月お給料はもらっているはずなのに、なぜか月末にはお金が残っていない」
「何にいくら使っているのか、実はよく分かっていない」
「貯金をしたいけれど、どこから手をつければいいか分からない」
高校生や社会人になったばかりの頃、こうしたお金の悩みを抱える人は少なくありません。アルバアや新社会人としての収入は、自分で自由に使えるお金が増える喜びと同時に、自己管理の責任も伴います。
この「なんとなくお金が足りない」という漠然とした不安を解消する最も確実で基本的な方法が、「家計簿をつけること」です。
しかし、家計簿と聞くと「面倒くさい」「細かくて続かない」「節約ばかりで息が詰まりそう」といったネガティブなイメージを持つ人もいるかもしれません。
この記事では、なぜ今、家計簿をつける必要があるのか、その本当の目的とメリットを徹底的に解説します。家計簿は単なる節約ツールではなく、自分のお金の流れを把握し、将来の資産形成(資産を築いていくこと)に繋げるための強力な武器です。
この記事を読めば、家計簿の目的とメリットが明確に理解でき、自分に合った継続しやすい方法を見つけるヒントが得られるはずです。

家計簿は「なんとなく」をお金の世界から追い出すための最強のツールです。まずは自分の現在地を知ることから始めましょう。
家計簿とは?お金の流れを「見える化」する第一歩
家計簿とは、一言でいえば「家庭のお金の出入り(収入と支出)を記録する帳簿」のことです。いつ、何に、いくらお金を使ったのか、そして、いくら収入があったのかを記録していきます。
多くの人が誤解しがちなのですが、家計簿をつける目的は「記録すること」そのものではありません。毎日1円単位で完璧に記録し、美しい帳簿を完成させることがゴールではないのです。
家計簿の最も基本的かつ重要な目的は、自分のお金の流れを「見える化」し、現状を正確に把握することです。
私たちは毎日、意識的にも無意識的にもお金を使っています。コンビニでのちょっとした買い物、友人とのランチ代、サブスクリプション(月額課金)サービスの利用料、スマートフォンの通信費など、支出の経路は多岐にわたります。これらが積み重なった結果、月末に「何に使ったか分からないけれど、お金がない」という状況が生まれます。
家計簿は、このブラックボックス化しがちな支出を客観的なデータとして示してくれます。
- 収入(入): 給与、アルバア代、副業収入、お小遣いなど
- 支出(出): 食費、住居費、光熱費、通信費、交際費、趣味・娯楽費など
これらを記録することで、「自分は月にいくら稼ぎ、何にいくら使っているのか」というお金の全体像を、数字で冷静に把握できるようになります。
税金の計算(確定申告など)のために家計簿(会計帳簿)が必要な場合もありますが、ほとんどの高校生や社会人初級者にとっての第一の目的は、この「現状把握」です。
現状が分からなければ、改善策を立てることも、将来の計画(例えば「1年後に10万円貯める」や「留学費用を準備する」など)を立てることもできません。家計簿は、自分のお金の健康状態を知るための「健康診断書」のようなものなのです。

家計簿の目的は「反省」ではなく「発見」です。何にいくら使ったかを知ることで、初めて「じゃあどうするか」を考えられます。
家計簿をつける3つのメリットと節約効果
家計簿をつけてお金の流れを「見える化」すると、具体的にどのような良いことがあるのでしょうか。ここでは、家計簿をつけることによって得られる主な3つのメリットを解説します。
メリット1:支出の全体像を正確に把握できる
家計簿をつける最大のメリットは、感覚ではなく「事実」として、自分のお金の使い道を把握できることです。「食費は月3万円くらいかな」と思っていたら、実際は5万円も使っていた、というケースは珍しくありません。
特にキャッシュレス決済(クレジットカードや電子マネー、QRコード決済など)が主流になると、現金が減る感覚が薄れ、支出を把握しにくくなります。家計簿は、これらの支出もすべて一つの場所に集約し、客観的なデータとして可視化してくれます。
メリット2:無駄な出費(浪費)を発見できる
支出の全体像が分かると、次に「無駄な出費」がどこに潜んでいるかが見えてきます。
例えば、以下のような項目です。
- ほとんど利用していないサブスクリプションサービスの月額料金
- 「なんとなく」毎日買っているコンビニの飲み物やお菓子
- 高額な手数料がかかる時間帯のATM利用
- 買ったけれど使っていない服や雑貨
これらは一つひとつが少額でも、積み重なると大きな金額になります。家計簿では、こうした「使途不明金」や「必要性の低い支出(浪費)」が明確になります。
この「無駄の発見」こそが、家計改善の第一歩です。どこに問題があるか分からなければ、節約のしようがありません。
メリット3:節約・貯蓄への意識が高まる
自分の支出パターンと無駄な部分が分かると、自然と「この支出は本当に必要か?」と考える習慣が身につきます。
家計簿をつけるという行為自体が、自分のお金に対する意識(金融リテラシー)を高めるトレーニングになります。「無駄遣いをやめよう」と漠然と思うだけでは行動は変わりませんが、家計簿で「今月はカフェ代に1万円も使っている」という事実を突きつけられると、「来月は5,000円に抑えよう」という具体的な行動目標につながります。
この節約や貯蓄への意識改革(マインドの変化)こそが、家計簿がもたらす非常に大きなメリットです。
ただし、注意点もあります。家計簿はあくまで「支出を管理」し、「無駄を発見」するためのツールです。家計簿をつけたからといって、自動的に収入が増えるわけではありません。家計簿のメリットは、主に「支出の最適化」にあることを理解しておきましょう。

「使途不明金」は家計のブラックホールです。家計簿でこの穴をふさぐことが、貯蓄体質への第一歩となります。
家計簿のつけ方ガイド:アプリ・ノート・PCソフトの比較
家計簿の重要性は分かったけれど、具体的にどうやってつければいいのでしょうか。家計簿をつける方法は、大きく分けて3つあります。それぞれの特徴を比較し、特に初心者におすすめの方法を紹介します。
1. 手書きノート
昔ながらの方法で、大学ノートや専用の家計簿ノートに手書きで記録していきます。
- メリット: 自分の好きなようにレイアウトでき、電卓で計算する過程で数字に強くなる。「書く」ことで支出を実感しやすい。
- デメリット: すべて手作業(計算、集計)のため時間がかかる。レシートが溜まると入力が億劫になりやすい。グラフ化などが難しい。
2. PCソフト(表計算ソフトなど)
Excel(エクセル)などの表計算ソフトや、市販のPC用家計簿ソフトを使って管理する方法です。
- メリット: 自動で計算・集計・グラフ化ができる。関数などを使えば自分好みにカスタマイズしやすい。
- デメリット: PCを起動する必要があり、入力が後回しになりがち。設定が複雑だと感じる場合がある。
3. スマートフォンアプリ
現在、最も主流な方法です。無料で高機能な家計簿アプリがたくさんあります。
- メリット: いつでもどこでもスマホで簡単に入力できる。レシートを撮影するだけで自動入力できる機能や、銀行口座・クレジットカードと連携して支出を自動で取り込む「自動連携機能」がある。
- デメリット: 種類が多すぎてどれを選べばいいか迷う。自動連携に抵抗がある人もいる。
初心者に最もおすすめなのは「スマホアプリ」
これから家計簿を始める高校生や社会人初級者の方には、圧倒的に「スマートフォンアプリ」をおすすめします。
理由は「手間が最もかからない」からです。
家計簿で最も重要なのは「継続すること」ですが、多くの人が挫折する原因は「入力が面倒」になることです。特に、完璧に記録しようとして費目(食費、交際費などの分類)を50個も作ったり、1円単位で合わせようとしたりすると、すぐに疲れてしまいます。
その点、スマホアプリ、特に「自動連携機能」が豊富なアプリを使えば、クレジットカードや電子マネーでの支払いの多くが自動で記録されます。現金で支払った分だけレシートを撮影したり、手入力したりすれば良いため、入力の手間が劇的に減ります。
まずは自動連携できるアプリを使い、「ざっくりと」支出を把握することから始めるのが、挫折しないための最も賢い選択です。

家計簿は「方法」が目的になってはいけません。自分が最もストレスなく続けられるツールを選ぶことが、成功の9割を占めます。
家計簿が続かない最大の理由と挫折しないためのコツ
「家計簿をつけ始めたけれど、三日坊主で終わってしまった」という経験は、多くの人が通る道です。なぜ家計簿は続かないのでしょうか。その最大の理由と、挫折しないための具体的なコツを解説します。
挫折の最大の理由:完璧主義
家計簿が続かない最大の理由は、「完璧主義」です。
- 1円単位で残高を合わせようとする
- 費目を細かく分類しすぎる(例:「食費」を「朝食」「昼食」「夕食」「お菓子」などに分ける)
- 毎日必ず記録しないと気が済まない
こうした完璧主義は、最初のうちは達成感がありますが、次第に記録すること自体が大きなストレスになります。一度でもレシートをなくしたり、計算が合わなかったりすると、「もう面倒だ」と投げ出してしまうのです。
家計簿の目的は、会計監査のように1円単位で正確な帳簿を作ることではなく、「お金の大まかな流れを把握し、無駄を見つけること」です。多少の誤差(数百円程度)は気にしない「ずぼらさ」も、継続のためには必要です。
挫折しないための3つのコツ
完璧主義の罠に陥らず、家計簿を継続するための3つのコツを紹介します。
コツ1:完璧を目指さない(1円単位は不要)
月に数回、使途不明金が数百円出ても問題ありません。レシートがない支出は「雑費」としてまとめて計上するなど、大らかに構えましょう。大切なのは、1円の誤差より「食費にいくら使っているか」という傾向を掴むことです。
コツ2:費目を細かくしすぎない
最初は「固定費(家賃、光熱費、通信費など)」と「変動費(食費、交際費、趣味費など)」に分けるだけでも十分です。多くても10項目程度に絞り込み、自分が管理しやすいシンプルな分類にしましょう。
コツ3:記録を溜めない(まとめて記録もOK)
毎日記録するのが理想ですが、難しければ「週末にまとめて記録する」「給料日前に一度だけ記録する」など、自分のライフスタイルに合わせたルールを決めましょう。スマホアプリの自動連携を使えば、この手間も大幅に削減できます。
家計簿は「つけるだけで満足」してしまいがちですが、大切なのは記録したデータを「見返す」ことです。継続することを最優先に、自分にとって無理のない方法を見つけましょう。

100点を目指して0点になるより、60点でいいから続けることが大切です。家計簿は「継続」こそが最大の価値を生みます。
家計簿の最終ゴール:支出把握から資産管理へ
家計簿をつけて支出を把握し、無駄を減らして節約する。これは非常に重要なステップですが、家計簿の本当のゴール(最終目的)は、実はその先にあります。
家計簿の最終ゴールは、「収支を安定的に黒字化し、その余剰資金(余ったお金)を将来のために貯蓄や投資に回し、資産形成に繋げること」です。
家計簿は、お金の「守り」のツールです。支出をコントロールすることで、家計の赤字を防ぎ、黒字(収入>支出)の状態を目指します。
しかし、ただ節約して支出を切り詰めること(Q5の選択肢A)がゴールではありません。それでは生活が窮屈になるだけです。
家計簿によって「毎月いくらお金が余るか(あるいは足りないか)」が明確になれば、次のステップに進めます。
- 収支のバランス(黒字化)を確認する: まずは安定して黒字になることを目指します。
- 貯蓄目標や投資計画を立てる: 「毎月3万円余るから、2万円は貯金して、1万円は投資(例:つみたてNISAなど)に回そう」といった具体的な計画を立てられます。
- 家計改善のPDCAを回す: 計画(Plan)を実行(Do)し、家計簿で結果を振り返り(Check)、改善(Action)する。このサイクルを回すことで、家計はより強固になります。
家計簿は、お金の「守り」を固めることで、将来の資産を増やす「攻め」(資産形成)への土台を作るための、最も基本的で重要なツールなのです。家計簿アプリの全機能を使いこなすこと(Q5の選択肢D)が目的ではなく、そのデータを使ってどう行動するかが問われます。

家計簿は「守り」の道具であると同時に、「攻め」の戦略マップでもあります。黒字化した分をどう増やすか、未来の計画を立てましょう。
まとめとやるべきアクション
今回は、家計簿をつける目的とメリット、そして継続のコツについて解説しました。
- 家計簿の目的: 記録自体ではなく、お金の流れを「見える化」し「現状把握」すること。
- 家計簿のメリット: 支出を把握し、無駄を発見でき、節約・貯蓄への意識が高まる。
- 継続のコツ: 完璧主義を捨て、スマホアプリなどを活用し「ざっくりと」でも継続する。
- 最終ゴール: 収支を黒字化し、余剰資金を貯蓄や投資に回して「資産形成」に繋げること。
家計簿は、自分のお金と向き合い、将来の不安を減らし、夢を実現するための第一歩です。
この記事を読んで「家計簿を始めてみよう」と思った方は、ぜひ今日から具体的なアクションを起こしてみましょう。
最初の一歩として、まずは1週間、自分が使ったお金のレシートやキャッシュレス決済の履歴をすべて集め、何にいくら使ったかをノートやアプリに書き出してみてください。
その1週間のデータを見るだけでも、きっと新しい発見があるはずです。

家計簿は、あなたの「お金の健康診断書」です。まずは1週間の支出を書き出すという「小さな一歩」から、未来の資産形成を始めましょう。
このページの内容の理解度をクイズでチェック!
免責事項
本記事は、一般的な企業・業界情報および公開資料等に基づく執筆者個人の見解をまとめたものであり、特定の銘柄や金融商品への投資を推奨・勧誘するものではありません。また、記事内で取り上げた見解・数値・将来予測は、執筆時点の情報に基づくものであり、その正確性・完全性を保証するものではありません。今後の市場環境や企業動向の変化により、内容が変更される可能性があります。
本記事に基づく投資判断は、読者ご自身の責任と判断において行ってください。 本記事の内容に起因して生じたいかなる損失・損害についても、当サイトおよび執筆者は一切の責任を負いません。本記事は金融商品取引法第37条に定める「投資助言」等には該当せず、登録金融商品取引業者による助言サービスではありません。