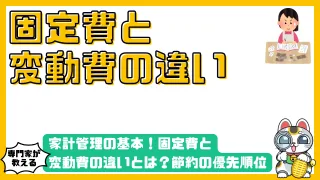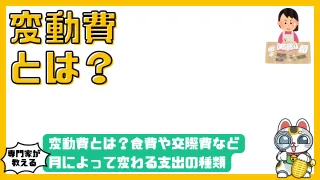本ページはプロモーションが含まれています。
このページの内容の理解度をクイズでチェック!
目次
はじめに
「毎月お給料やアルバイト代が入っても、月末にはなぜかお金が残っていない」
「節約を頑張っているつもりなのに、一向に貯金が増えない」
そんな悩みを抱えている高校生や新社会人の皆さん、もしかしたらその原因は、あなたの家計に潜む「固定費(こていひ)」にあるかもしれません。
固定費とは、私たちが生活していく上で(半ば自動的に)毎月ほぼ一定額出ていく支出のことです。この固定費を正しく理解し、管理することは、家計簿をつける上で、そして将来の資産を築いていく上で、最も重要なスキルの一つと言えます。
この記事では、「固定費」には具体的にどのような種類があるのか、なぜそれを見直すことが家計改善の「最強の近道」になるのかを、一つひとつ丁寧に解き明かしていきます。この記事を読み終える頃には、あなたの家計簿を見る目が変わり、節約への「最初の一歩」が明確になっているはずです。

家計管理は「敵」を知ることから始まります。あなたの家計における最大の「敵」であり、同時に最強の「味方」にもなり得るのが、この「固定費」です。まずはその正体をしっかり学びましょう。
最大の固定費:住居費
家計の支出の中で、最も大きな割合を占めることが多いのが、この「住居費(じゅうきょひ)」です。固定費の代表格であり、まさに家計の土台そのものです。
住居費とは?
固定費の基本的な定義は、「あなたの毎月の活動量(例:外食を何回したか、旅行に行ったか)に関わらず、ほぼ一定額が出ていく支出」のことです。
住居費は、この定義に完璧に当てはまります。あなたが家で過ごす時間が長くても短くても、契約で決められた家賃やローンは毎月必ず発生します。
- 家賃: アパートやマンションの賃貸料。
- 住宅ローン: 家を購入した場合の毎月の返済額。
- その他: 管理費、共益費、駐車場代、町内会費なども、毎月定額であれば住居費(固定費)に含まれます。
なぜ最重要なのか?
住居費が家計改善において最重要視される理由は、単純明快です。それは「家計に占める割合(支出シェア)が最も大きいことが多い」からです。
一般的に、家賃は手取り収入の3割程度が目安と言われることもありますが、新社会人や都市部での一人暮らしの場合、この割合がさらに高くなることも珍しくありません。
支出の「土台」である住居費が大きいと、他の支出(食費や交際費など)をいくら切り詰めても、なかなか貯蓄に回す余裕が生まれません。
見直し効果は絶大
この住居費は、「一度決めたら変えられない」(mis#5)と諦めがちですが、もし見直すことができれば、その節約効果は絶大です。
例えば、家賃が今より5,000円安いところに引っ越す、あるいは(持ち家の場合)住宅ローンの借り換えで毎月の返済額が5,000円減ったとします。それは、一度の手続きで年間60,000円の節約が(何もしなくても)自動的に続くことを意味します。
日々の食費を切り詰める努力と比べ、その効果がいかに大きいかが分かるはずです。

住居費は家計の「土台」です。この土台が不安定(高すぎる)だと、その上でどんなに節約を頑張っても家計は安定しません。自分の収入に見合った適切な住居費を維持することが、すべての基本です。
生活インフラ費:通信費と光熱費の分類
私たちが現代生活を送る上で欠かせない、電気・ガス・水道やスマートフォン。これらの「生活インフラ費」も、固定費管理において非常に重要な項目です。
通信費(スマホ代・ネット代)
スマートフォンの利用料金や、自宅のインターネット(Wi-Fi)回線の料金も、主要な固定費です。
これらも、毎月のデータ使用量に関わらず「基本料金」や「定額プラン料」が発生するため、固定費に分類されます。特に、大手通信キャリアで高額なプランを契約したままにしていると、家計をじわじわと圧迫します。
格安SIMへの乗り換えや、自分の利用状況に合ったプランへの見直し、不要なオプションの解約は、住居費の次に見直し効果が出やすいポイントです。
「準変動費」としての光熱費
ここで、多くの人が迷うのが「光熱費(こうねつひ)」(電気・ガス・水道代)の扱いです。
「光熱費は使った分だけ払うのだから、変動費ではないか?」(mis#1)という誤解がありますが、厳密にはこれは「準変動費(じゅんへんどうひ)」と呼ばれるものです。
「準変動費」とは、固定費の性質と変動費の性質が混在している費用のことを指します。
光熱費の請求書をよく見てみると、その内訳は以下のようになっています。
- 基本料金(固定費の要素): まったく電気やガスを使わなかったとしても、契約しているだけで毎月必ず発生する料金。
- 使用量料金(変動費の要素): あなたが実際に使った電気やガスの量に応じて加算される料金。
(クイズの答え:光熱費が準変動費と呼ばれるのは、この「基本料金(固定)」と「使用量料金(変動)」の両方が含まれているためです。)
家計管理上の「光熱費」の扱い
このように厳密には準変動費ですが、家計管理の実務上は「毎月必ず発生する最低支払額(基本料金)がある」という点、そして「生活に必須でゼロにはできない」という点から、固定費(または固定費に近いもの)として分類し、管理するのが一般的です。
見直しのポイントとしては、「基本料金」部分(電力会社やガス会社の切り替え、契約アンペア数の見直し)と、「使用量料金」部分(日々の節電・節水)の両方からアプローチできるのが特徴です。

スマホ代や光熱費は「当たり前」に払っているため、見直しの対象外と考えがちです。しかし、今は電力会社も通信会社も自由に選べる時代。この「インフラ費」にメスを入れることが、賢い家計管理の第一歩です。
将来への備え:保険料という固定費
病気やケガ、万が一の事態に備えるための「保険料」も、毎月決まった額を引き落とされる、典型的な固定費の一つです。
保険料が固定費である理由
保険は「契約」に基づいて成り立っています。あなたが健康であろうとなかろうと、契約を継続する限り、毎月(あるいは毎年)一定額の保険料を支払う義務が発生します。
この「契約に基づき、毎月一定額の支払いが発生する」という性質が、保険料を固定費たらしめる理由です。
- 生命保険: 死亡時に家族にお金を残すための保険。
- 医療保険: 病気やケガでの入院・手術に備える保険。
- 損害保険: 自動車保険(対人・対物事故への備え)や、火災保険(家の火事や災害への備え)など。
(クイズの答え:例えば「毎月払う生命保険料」は、このような契約に基づく定額支払いであるため、固定費に分類されます。一方、「コンビニで買ったお菓子代」や「カフェ代」「都度の電車代」は、その日の行動によってゼロにもできる「変動費」です。)
「掛け捨て」と「積立」
保険には、大きく分けて「掛け捨て(かけすて)」と「積立(つみたて)」の2種類があります。
- 掛け捨て: 支払った保険料が、保障(万が一の時の保険金)のためだけに使われ、解約してもお金は戻ってこないタイプ。保険料は比較的安価です。
- 積立: 保障機能と同時に、貯蓄の機能も持つタイプ。解約時や満期時にお金が戻ってくる(解約返戻金や満期保険金)可能性がありますが、保険料は高額になりがちです。
家計管理上は、どちらも「固定費」として扱いますが、「積立」タイプの保険は「貯蓄」としての側面も持つ、と理解しておくと良いでしょう。

保険は「お守り」として必要なものですが、その「お守り」にいくら払うかは慎重に決めるべきです。特に新社会人の場合、本当に必要な保障は何か、親の保険はどうなっているかなどを確認し、過剰な固定費にならないよう注意が必要です。
見落としがちな固定費:サブスクリプションの罠
家賃や保険料といった高額な固定費とは別に、近年急速に家計を圧迫する要因となっているのが、見落としがちな固定費、「サブスクリプション(定額制サービス)」です。
「チリツモ」の代表格
サブスクリプションとは、商品やサービスを「買い切る」のではなく、「利用した期間に応じて料金を支払う」方式のことです。
- 具体例:
- 動画配信サービス(Netflix, Amazon Prime Videoなど)
- 音楽配信サービス(Spotify, Apple Musicなど)
- 雑誌・電子書籍の読み放題サービス
- スマートフォンのアプリ課金(ゲーム、便利ツールなど)
- フィットネスジムやオンラインレッスンの月会費
- ソフトウェアやクラウドストレージの利用料
これらは、一つひとつの月額料金が数百円から千円程度と少額なことが多いため、「これくらいならいいか」と契約してしまいがちです。
サブスク管理の注意点
しかし、この「少額」というのが最大の罠です。
「サブスクは少額だから固定費と考えなくてよい」(mis#4)と管理対象から外してしまうと、どうなるでしょうか。
例えば、月額500円のサービスを5つ契約していたとします。1つは少額でも、合計では毎月2,500円。これが年間では30,000円もの支出になります。これが「チリも積もれば山となる(チリツモ)」の恐ろしさです。
(クイズの答え:サブスクリプションの家計管理上の注意点は、まさにこの「一つ一つは少額でも、複数契約することで家計を圧迫する大きな固定費になる」という点です。)
「一度契約すると絶対に解約できない」わけではなく、むしろ解約は簡単なサービスが多いです。だからこそ、使っていないサービス、利用頻度の低いサービスがないか、定期的に「棚卸し」をして、不要な契約は見直す勇気が必要です。

サブスクリプションは、あなたの生活を豊かにする「ツール」であると同時に、家計を静かに蝕む「寄生虫」にもなり得ます。本当にそのサービスに月額料金を払う価値があるのか、常に自問自答するクセをつけましょう。
固定費の把握が家計改善の第一歩
ここまで、代表的な固定費の種類を見てきました。家賃、通信費、光熱費(準変動費)、保険料、サブスク…。
しかし、固定費はこれだけではありません。
その他の固定費の例
人によっては、以下のようなものも毎月の固定費として発生しています。
- 奨学金の返済: 学生時代に借りた奨学金の毎月の返済額。
- 各種ローン: 車のローンや、高額な家電などを分割払いにした場合の支払い。
- 教育費・習い事: 自分の習い事の月謝、資格取得のためのオンライン講座費用など。
- 定期購入: 毎月届く健康食品や化粧品、コンタクトレンズなども固定費と言えます。
「固定費は家賃だけだ」(mis#3)と誤解していると、これら無数の「隠れ固定費」を見落とし、家計改善の機会を失ってしまいます。
固定費を把握する「最大の目的」
では、なぜ私たちはこんなにも細かく「固定費」の種類を把握する必要があるのでしょうか?
それは、「固定費は変えられないから諦めるため」でも、「毎月の支出を変動費だけにするため」でもありません。
固定費を正確に把握する最大の目的は、「家計改善(節約)の対象として、どこから手をつけるべきか、その『優先順位』をつけるため」です。(クイズの答え)
固定費は「変えられない」のではなく「変えにくい」だけ
家計改善の鉄則は、「変動費(食費など)の節約」から始めるのではなく、まず「固定費の見直し」から始めることです。
「固定費は一度決めたら絶対に変えられない」(mis#5)というのは、最大の誤解です。正しくは、「変えにくいが、一度変えれば効果が絶大で、それがずっと持続する」です。
食費(変動費)を毎月5,000円節約し続けるには、毎日の我慢が必要です。
しかし、固定費(スマホ代)を一度見直して毎月5,000円安くできれば、その節約効果は来月も再来月も、あなたが何もしなくても続きます。
だからこそ、家計改善の第一歩は、あなたが毎月何にいくら「固定費」を払っているのか、その種類と金額を正確に「把握」することなのです。

固定費の把握は、家計の「健康診断」です。どの項目(固定費)が家計を圧迫しているのか、その「病巣」を特定すること。それが、効率的な家計改善(治療)の始まりとなります。
まとめとやるべきアクション
今回は、家計管理の土台となる「固定費」の具体的な種類について、網羅的に解説してきました。
- 最大の固定費(住居費): 家賃や住宅ローン。家計に占める割合が最も大きい。
- インフラ費(通信・光熱費): スマホ代、ネット代。光熱費は「基本料金(固定)」と「使用量(変動)」が混在する「準変動費」。
- 備えの費用(保険料): 生命保険や自動車保険など、契約に基づく定額の支払い。
- 見落としがちな固定費(サブスク): 少額でも「チリツモ」で大きな負担になる定額制サービス。
- その他: 奨学金返済や各種ローン、月謝なども固定費。
これらの固定費を把握する最大の目的は、節約の「優先順位」をつけるためです。日々の変動費の節約(我慢)に走る前に、まず効果が持続する「固定費」を見直すこと。これが家計改善の鉄則です。
この記事を読んで「固定費の種類はわかった」で終わらせては、あなたの家計は1円も変わりません。ぜひ、今週末に「次の一歩」を踏み出してみましょう。
💡 今すぐできるアクションプラン
まず、先月(または今月)のあなたの支出を、銀行の通帳、クレジットカードの明細、家計簿アプリなどをすべて見返して書き出してください。
そして、この記事を参考に「これは固定費だ」と思う項目にマーカーを引き、その「固定費の合計金額」がいくらになっているか、計算してみましょう。
- 家賃:〇〇円
- スマホ代:〇〇円
- ネット代:〇〇円
- 光熱費(基本料金だけでも):〇〇円
- 保険料:〇〇円
- サブスクA:〇〇円
- サブスクB:〇〇円
- 奨学金返済:〇〇円
- 固定費 合計: ???円
まずは、自分の家計が毎月どれだけの「固定費」という名の重りを背負っているのか、その「総重量」を正確に知ることから、すべての家計改善は始まります。

固定費の合計額を知ることは、あなたの「家計の体力」を知ることです。その数字を見て「多すぎる」と感じたら、それがあなたの家WELCOME改善のスタートラインです。
このページの内容の理解度をクイズでチェック!
免責事項
本記事は、一般的な企業・業界情報および公開資料等に基づく執筆者個人の見解をまとめたものであり、特定の銘柄や金融商品への投資を推奨・勧誘するものではありません。また、記事内で取り上げた見解・数値・将来予測は、執筆時点の情報に基づくものであり、その正確性・完全性を保証するものではありません。今後の市場環境や企業動向の変化により、内容が変更される可能性があります。
本記事に基づく投資判断は、読者ご自身の責任と判断において行ってください。 本記事の内容に起因して生じたいかなる損失・損害についても、当サイトおよび執筆者は一切の責任を負いません。本記事は金融商品取引法第37条に定める「投資助言」等には該当せず、登録金融商品取引業者による助言サービスではありません。