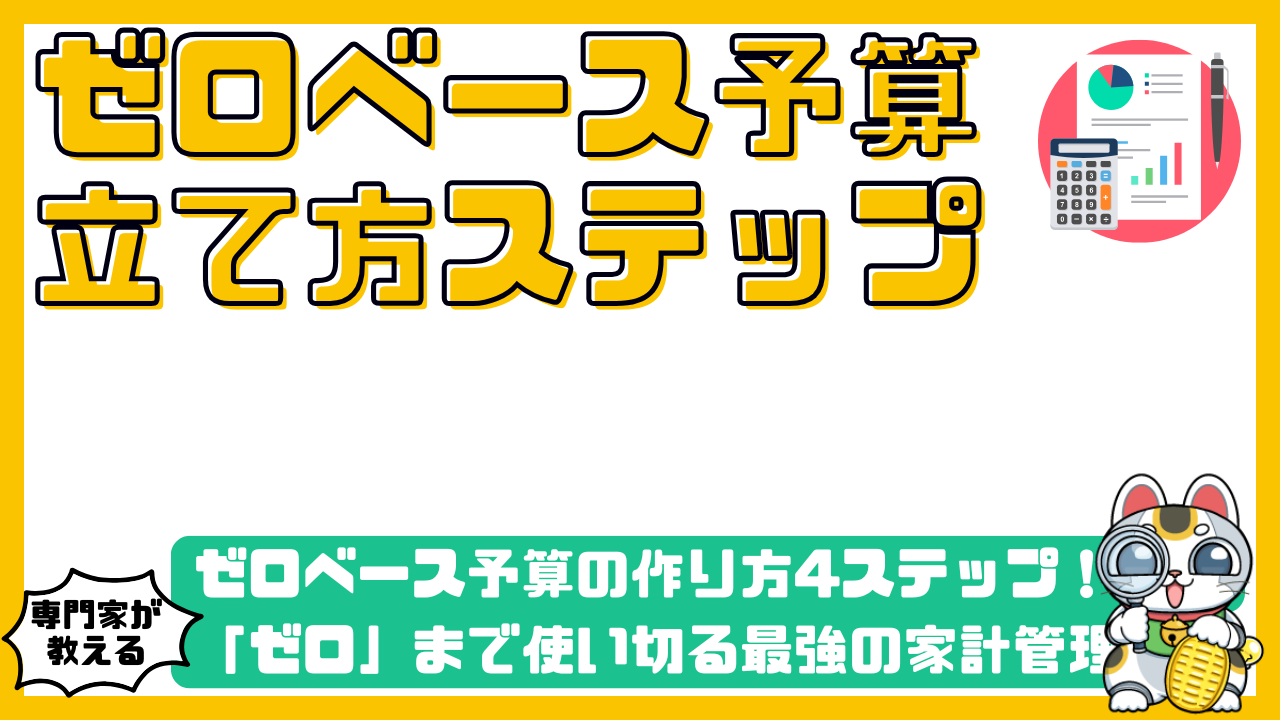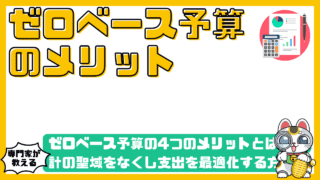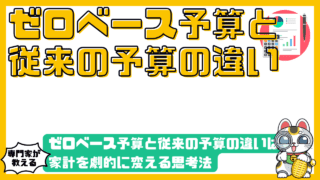本ページはプロモーションが含まれています。
このページの内容の理解度をクイズでチェック!
目次
はじめに
「今月も何となくお金を使ってしまい、給料日前はカツカツだ」
「家計簿をつけているけれど、ただ記録しているだけで節約につながっていない気がする」
「将来のために貯金したいけれど、生活費で精一杯で回らない」
もしあなたがそんなモヤモヤを抱えているなら、予算の立て方を根本から変えてみる必要があるかもしれません。多くの人が陥りがちな家計管理の罠、それは「結果の記録」に終始してしまうことです。レシートを集めて家計簿アプリに入力し、「今月も使いすぎたな」と反省する。これでは、過去を振り返っているだけで、未来を変える力は弱いです。
家計管理において最も重要なのは、「使ったお金を記録すること」ではなく、「使う前にお金の行き先を決めること」です。お金を使うという行為は、本来、あなたの意思決定の結果であるべきです。しかし、計画がないと、その場の感情や環境に流され、無意識の出費(浪費)が増えてしまいます。
そこで提案したいのが、「ゼロベース予算(Zero-Based Budgeting: ZBB)」という手法です。これは、毎月の手取り収入の全額に対して、あらかじめ「使い道」を割り振り、計算上の残高を「ゼロ」にするという、非常にロジカルで効果的な予算管理術です。
「収入を全部使い切ってゼロにするなんて、貯金はどうするの?」と不安に思うかもしれません。安心してください。ここで言う「使い切る」とは、無駄遣いすることではありません。将来のための貯金や投資も含めて、すべてのお金に「役割」を与えることを意味します。お金に「名前」をつけてあげることで、行方不明になるお金(使途不明金)をなくすのです。
本記事では、このゼロベース予算を実践するための具体的な4つのステップを、初心者にも分かりやすく解説します。収入の把握から支出の洗い出し、運命の割り振り作業、そして日々の実行・追跡まで。このプロセスを一度体験すれば、お金に対する漠然とした不安が消え、自分が家計のコントロールタワーに座っているという確かな感覚が得られるはずです。さあ、電卓とノートを用意して、一緒に始めましょう。

家計管理のゴールは、お金を貯めることだけではありません。自分のお金を自分の意思でコントロールできているという「自信」を持つことです。ゼロベース予算は、その自信を育てるためのトレーニングです。
Step 1:収入の把握 – 予算の土台を固める
ゼロベース予算の第一歩は、自分が「今月、実際にいくら使えるのか」を1円単位まで正確に把握することです。これが全ての計画の土台となります。土台がグラグラしていては、その上にどんな立派な予算を組んでも崩れてしまいます。
「手取り収入」を確認する
ここで言う「収入」とは、会社から提示される年収や、月給の「額面給与(総支給額)」ではありません。税金(所得税・住民税)や社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険など)が引かれた後の、銀行口座に実際に振り込まれる「手取り収入(可処分所得)」です。
多くの人が、自分の給料を「額面」で認識しています。「月給25万円だ」と思っていても、実際に使えるのは約20万円程度です。もし額面を基準に「家賃はこれくらい、食費はこれくらい」と予算を組んでしまうと、現実には存在しない5万円分まで使おうとしてしまい、最初から赤字の計画を立てることになります。
必ず給与明細の「差引支給額」や、通帳の振込額を確認してください。これが、あなたが今月自由に采配できる「パイ(資源)の総量」です。
不定期な収入も漏らさず計上
会社員の方であれば毎月の給料はほぼ一定かもしれませんが、以下のような収入がある場合は忘れずに合算しましょう。
- 副業収入: クラウドソーシング、アルバイト、ブログ収入などの手取り額。税金が引かれていない場合は、納税用のお金を取り分けてから合算します。
- 臨時収入: フリマアプリでの不用品売却益、還付金、お祝い金、児童手当など。これらも「ラッキーマネー」として無計画に使うのではなく、予算の一部として組み込みます。
- 前月からの繰越金: 先月の予算で余ったお金がある場合、それも今月の収入として扱います。
これら全ての「入ってくるお金」を合計した数字を、ノートの一番上に大きく書き出しましょう。これが今月のあなたの戦力です。
収入が変動する場合のコツ
フリーランスやシフト制のアルバイトなど、月によって収入が大きく変動する人はどうすればよいでしょうか。
コツは、「少なめに見積もる」ことです。過去数ヶ月の中で最も少なかった月の収入をベースに予算を組みます。もし実際に入ってきたお金がそれより多ければ、その差額は全額「貯蓄」や「予備費」に回せば良いだけです。逆に、多めに見積もって足りなくなると、生活が破綻します。予算作成においては、悲観的に準備し、楽観的に実行するのが鉄則です。

「だいたい20万円くらい」というアバウトな把握が、家計のズレを生む最大の原因です。1円単位まで数字を直視することが、現実的な予算作成のスタートラインです。
Step 2:支出の洗い出し – 固定費と変動費を可視化
収入が確定したら、次は「出ていくお金(支出)」の全貌を明らかにします。今月予定されている全ての支払いをリストアップしましょう。記憶だけで書くのではなく、過去の家計簿、クレジットカードの明細、銀行の引き落とし履歴などを見ながら、漏れがないように書き出します。
カテゴリー別に整理する
支出を闇雲に書き出すのではなく、大きく2つのカテゴリーに分けると管理しやすくなります。
- 固定費(Needs): 毎月決まった金額が自動的に出ていく支出です。生きるために不可欠なものが多く含まれます。
- 住居費: 家賃、管理費、住宅ローン、駐車場代。
- 水道光熱費: 電気、ガス、水道。季節によって変動しますが、生活インフラとして必須です。
- 通信費: スマホ代、自宅のネット回線、Wi-Fi料金。
- 保険料: 生命保険、医療保険、学資保険など。
- サブスクリプション: 動画配信サービス、音楽アプリ、ジムの会費、オンラインサロンなど。
- 教育費: 学校の授業料、給食費、習い事の月謝。
- 返済: 奨学金、車のローンなどの返済額。
- 変動費(Wants & Needs): 月によって金額が変わり、自分の行動次第で増減する支出です。
- 食費: 自炊のための食材費、外食費、カフェ代、コンビニ利用費。
- 日用品費: トイレットペーパー、洗剤、シャンプーなどの消耗品。
- 交通費: 電車やバスの運賃、ガソリン代、タクシー代。
- 交際費: 飲み会、ランチ会、プレゼント代、ご祝儀。
- 趣味・娯楽費: 映画、本、ゲーム、旅行、推し活費用。
- 被服・美容費: 洋服、クリーニング、美容院、化粧品。
- 医療費: 通院費、薬代。
特別費(年払いなど)への対応
家計管理を崩す最大の要因が、年に数回しかない高額出費(特別費)です。自動車税、年払いの保険料、車検、帰省費用、クリスマスのプレゼントなどがこれに当たります。
これらを支払う月になって慌てないように、年間でかかる費用をリストアップし、12で割った金額を「特別費積立」として毎月の支出リストに加えるのが上級テクニックです。
「貯金」も支出リストに入れる
ここがゼロベース予算の最大のポイントであり、パラダイムシフト(考え方の転換)が必要な部分です。
「貯金(Savings)」や「投資(NISA、iDeCoなど)」も、支出項目の一つとしてリストアップしてください。
従来の家計管理:「収入 − 生活費 = 貯金(残り)」
ゼロベース予算:「収入 −(生活費 + 貯金)= 0」
多くの人は「生活費を使って、残ったら貯金しよう」と考えがちですが、パーキンソンの法則(支出は収入の額まで膨張する)により、これでは確実に失敗します。
貯金や投資は、「未来の自分への支払い」という立派な支出です。家賃などの大家さんへの支払いと同じように、最初から「絶対に払うべきもの(サンクコスト)」としてリストに組み込みましょう。これを「先取り貯蓄」と呼びます。

リストアップは、自分の生活を映す鏡です。「こんなに使っていないはず」と思いたくても、明細という事実は嘘をつきません。まずは現状をありのままに受け止めることが改善への第一歩です。
Step 3:「0」への割り振り – ゼロベース予算の核心
収入と支出の洗い出しが終わったら、いよいよゼロベース予算の核心部分である「割り振り」作業に入ります。ここでのゴールは、計算式の結果をプラスマイナス「ゼロ」にすることです。
計算式:収入 −(全ての支出 + 貯蓄 + 投資)= 0
パズルのように予算を組む
Step 1で書き出した「手取り収入」というパイを、Step 2でリストアップした「支出」というお皿に配分していきます。優先順位をつけて配分するのがコツです。
- 固定費を引く: まずは、家賃や光熱費など、生きていくために払わなければならない固定費を収入から差し引きます。これらは減らすのが難しいため、最初に確保します。
- 貯蓄・投資を引く(先取り): 次に、未来のための貯蓄や投資の予算を引きます。手取りの10%〜20%を目安に確保するのが理想ですが、最初は無理のない範囲で構いません。しかし、必ず「0」にはせず、少額でも確保します。
- 変動費に割り振る: 残った金額を、食費、日用品費、趣味などの変動費に割り振っていきます。ここで、各項目の予算額を決定します。
黒字(余り)が出た場合
すべての必要な項目に割り振っても、まだ計算上お金が余っている場合。「ラッキー!これは自由に使おう」と放置してはいけません。ゼロベース予算では、役割のないお金(遊んでいるお金)を許しません。その余剰金にも必ず「名前(役割)」を与えます。
- 予備費: 急な医療費や冠婚葬祭、家電の故障に備えてプールしておく。
- 特別費積立: 来年の旅行や、数年後の車の買い替えのために積み立てる。
- 追加投資: NISAの積立額を増やす、あるいは個別の株式購入資金にする。
- Wantsの上乗せ: ずっと欲しかった高価なものを買うための資金にする。
このように、1円たりとも「使途不明金(迷子のお金)」を出さないように割り振ります。これにより、無意識の浪費を防ぐことができます。
赤字(不足)になった場合
逆に、計算の途中でマイナスになってしまった場合。例えば、収入20万円に対して、希望する支出を足していったら22万円になってしまったようなケースです。
これは、予算の段階で生活レベルが収入を超えているという明確な警告です。現実を直視し、修正(調整)が必要です。
- 変動費を削る: 「今月は外食を月2回に減らして食費を5,000円削ろう」「服を買うのは来月にして被服費をゼロにしよう」。Wants(欲しいもの)の項目は調整しやすい部分です。
- 固定費を見直す: 「サブスクを一つ解約しよう」「スマホのプランを下げよう」。固定費の削減は効果が持続します。
- 収入を増やす: どうしても削れない場合は、不用品を売る、短期バイトをするなど、収入(Step 1)を増やす方法を考えます。
数字が「ゼロ」になるまで、パズルのピースを入れ替えるように調整を繰り返してください。この「あちらを立てればこちらが立たず」という葛藤こそが、お金に対する優先順位を明確にし、金銭感覚を鍛えるトレーニングになります。
貯金を諦めない
赤字になった時、真っ先に「じゃあ今月は貯金なしで」と貯蓄額を削るのは避けましょう。貯金は「未来の自分を守るための支出」です。現在の楽しみ(Wants)を削ってでも、少額でも良いので貯金の枠は死守する姿勢が、強い家計を作ります。

「余らせない」ことが重要です。お金は空白を嫌います。使い道が決まっていないお金は、必ず無駄遣いという形で消えていきます。すべてのお金に行き先を指定してあげましょう。
Step 4:実行と追跡 – 計画を現実に変える
完璧な予算(計画)ができても、実行できなければ絵に描いた餅です。最後のステップは、作成した予算通りに生活し、その結果を記録(追跡)することです。
予算を守るための「封筒積立」
ゼロベース予算と相性が抜群なのが、「封筒積立(封筒分け)」という管理術です。
食費や交際費、趣味代など、現金で管理する変動費の予算額を、それぞれの費目を書いた封筒に入れます。
「今月の食費は3万円」と決めたら、3万円を食費の封筒に入れ、「この封筒の中身だけで1ヶ月やりくりする」と決めます。
財布にお金がなくなったらATMで引き出すのではなく、封筒から補充します。封筒の中身が減っていくのが可視化されるため、「あとこれだけしかない」という意識が働き、自然とブレーキがかかります。
キャッシュレス派の人は、銀行口座の「目的別口座」機能(住信SBIネット銀行など)や、家計簿アプリの予算設定機能を活用して、「デジタル封筒」として管理しましょう。
記録と追跡(トラッキング)
生活を始めたら、日々の支出を記録します。レシートを溜め込まず、スマホアプリなどでその都度入力するのがおすすめです。
そして、週に一度は進捗を確認しましょう。これを「ウィークリー・チェックイン」と呼びます。
「食費がペースオーバー気味だな。来週は自炊を増やそう」
「交際費はまだ余裕があるな。週末は友人を誘おうか」
月末にまとめて確認しても、使いすぎた事実は変えられません。週単位で軌道修正することが、予算を守り抜くコツです。
柔軟な調整(リ・バジェット)
もし、どうしても予算オーバーしそうな項目が出てきたらどうすればよいでしょうか。
例えば、急な飲み会が入って交際費が足りなくなった場合。
その時は、他の項目から予算を融通します。
「交際費が5,000円足りないから、今月の被服費の予算5,000円をこっちに回そう」
ゼロベース予算は「一度決めたら絶対に変えてはいけない」というガチガチのルールではありません。総額の中でプラスマイナスゼロが保たれていればOKです。この「予算の移動」を行うことで、赤字を出さずに乗り切ることができます。
月末の振り返りと次月への反映
月末になったら、結果を振り返ります。
「なぜ食費が予算オーバーしたのか?(外食が多かった?食材を買いすぎた?)」
「予算が余った項目はあったか?」
この反省を、翌月の「Step 3:割り振り」に活かします。
「来月は食費の予算を少し増やして、その分趣味代を減らそう」
このようにPDCAサイクルを回すことで、あなたの予算の精度は月を追うごとに高まり、自分にとって心地よい黄金比が見つかっていきます。

予算は「守るもの」というより「ガイドライン」です。道に迷わないための地図のようなものです。多少ルートを外れても、最終的に目的地(収支ゼロ)にたどり着ければ成功です。
まとめ:ステップ3が核心 – 意識的なお金の使い方へ
本記事では、ゼロベース予算を作成するための4つのステップについて解説しました。
- Step 1 収入の把握: 手取り収入を1円単位まで正確に知り、予算の総枠を確定させる。
- Step 2 支出の洗い出し: 固定費、変動費に加え、貯金や投資も「支出」としてリスト化する。
- Step 3 「0」への割り振り: 収入から支出を引き、すべての余剰金をなくして残高ゼロにする(最重要)。
- Step 4 実行と追跡: 封筒分けなどで予算を実行し、記録・調整しながら守り抜く。
この中で最も重要なのは、Step 3の「割り振り」です。
「なんとなく使う」のではなく、「すべての支出に意図を持つ」こと。これこそがゼロベース予算の本質であり、お金の不安を解消する鍵です。自分のお金に自ら指示を出し、コントロール下に置く感覚は、一度味わうと病みつきになるほどの安心感をもたらします。
最初は計算が合わなかったり、面倒に感じたりするかもしれません。しかし、慣れれば毎月30分程度の作業です。そのわずかな時間が、あなたの家計を劇的に改善し、理想の未来(貯金や投資の成功)を引き寄せる力になります。
【今すぐできるアクション】
まずは、先月の給与明細を取り出し、「手取り収入」を確認することから始めてみませんか? そして、その金額をどう使ったか思い出してみてください。もし「何に使ったか分からないお金」があれば、来月はゼロベース予算を試すチャンスです。あなたも今日から、自分のお金の「司令官」になりましょう。

金利が低いからこそ、手数料というコストをいかに削減するかが重要です。優遇条件を理解し、最もお得に使える方法を見つけることが、賢い金融生活の第一歩となります。
このページの内容の理解度をクイズでチェック!
免責事項
本記事は、一般的な企業・業界情報および公開資料等に基づく執筆者個人の見解をまとめたものであり、特定の銘柄や金融商品への投資を推奨・勧誘するものではありません。また、記事内で取り上げた見解・数値・将来予測は、執筆時点の情報に基づくものであり、その正確性・完全性を保証するものではありません。今後の市場環境や企業動向の変化により、内容が変更される可能性があります。
本記事に基づく投資判断は、読者ご自身の責任と判断において行ってください。 本記事の内容に起因して生じたいかなる損失・損害についても、当サイトおよび執筆者は一切の責任を負いません。本記事は金融商品取引法第37条に定める「投資助言」等には該当せず、登録金融商品取引業者による助言サービスではありません。